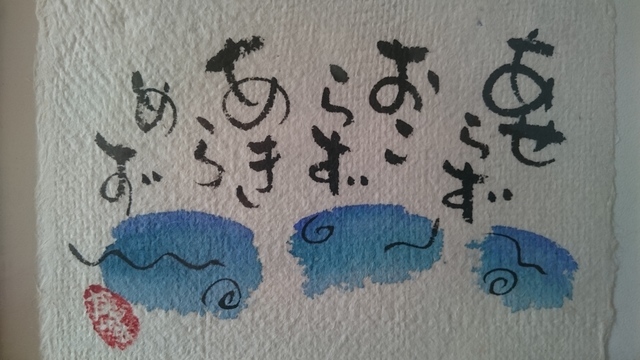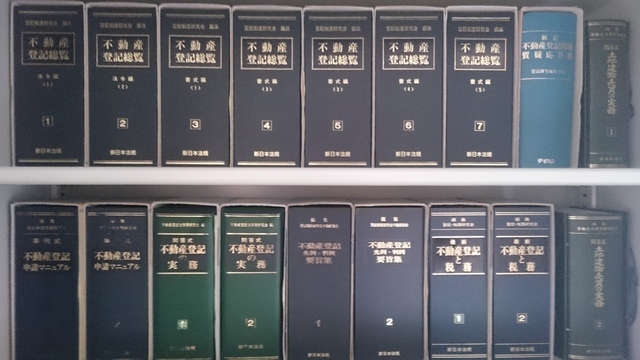0772-45-1686
平成29年債権法の改正について
(令和6年12月30日更新)

民法改正は相続法だけではなく、「債権法」も含まれます。
令和2年4月1日に施行されました。
その多くは過去の判例や実務を反映した内容となっていますが、大きく変わった点もあります。
例えば消滅時効の期間でしょう。
10年の期間が「5年」になる等、一般の生活でも影響があると思われます。
法定利息も年5%から「年3%」に変更されます。
その他、「契約の解除」「危険負担」「保証債務」「相殺」「定型約款」「売買」「消費貸借」「賃貸借」等が一般消費者には影響があると思われます。
消滅時効について

民法で規定されていた原則「10年」の消滅時効期間が、原則「5年」に短縮されました。
その他、短期消滅時効、商事消滅時効の規定が削除されました。
はい、そうですね。
意味が良く分かりませんよね?
なので具体的に
例えば、友人にお金を貸していた場合、今までは10年は「返して」といえたけど、今後は「5年」経ったら言えなくなるということです。
ちなみに、短期消滅時効に関しては、1月以下の期間で労働している方の賃金債権が「1年」だった旧民法174条が削除されました。
では、その1年が5年になったのか?と言いますとそうではなくて、労働基準法(同法第115条)に基づく賃金請求権は2年のままです。
知らないと損をするのが世の常なのでしょうか。
ただ、今言えることは、
債権をお持ちの方は、近々にご請求されることをお勧めしますということです。
では、お金を支払ってもらう方は保護されないのか?
と思いますよね。
その件については、時効の「停止」「中断」は、「完成猶予」「更新」という表現に改められ、改正されました。
今までは訴えの却下とか取下げがあった場合は、時効の中断は生じなかったのですが(つまり、何にもなかったことにして時効が成立してしまったのですが)、そういった事項(訴えの取り下げ等)が生じても6か月間は時効の完成が猶予される等、の法改正もされています。
「権利に関しての協議を行う旨の合意が書面でなされている」と、消滅時効の完成が猶予されるという内容の法改正もなされています(改正民法151条)。
なお、この法律は令和2年4月1日に施行されました。
賃貸借契約について
「敷金」や「原状回復」義務について

改正民法の中で、私たちの身近な生活に関するものとして、「賃貸借契約」があります。
例えばアパートを借りるときに預ける「敷金」とは何か?
新法では、賃借人が賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で交付する金銭は、その名目や授受の時期にかかわらず、すべて「敷金」として扱う、と定義づけられました。
今までは大家が「権利金」としてもらったお金だから「敷金」ではない、だから借主が退去する時に返さない、等といった争いが多かったので改正されたのですね。
また賃貸借契約書に記載される「原状回復」とは何か?
新法では、賃借人に帰責事由のない損傷や通常の損耗あるいは経年劣化については、原則「賃貸人の負担」となることが明文化されました。
今までは、普通に生活しているのに生じる、畳の日焼けであるとか、クロスの色あせ等を理由にして、新品に取り換える費用も、借主が退去時に請求され、争いが多かったので改正されたのですね。
「敷金」返還請求や「原状回復」義務等の争いは多いので、覚えておいてください。