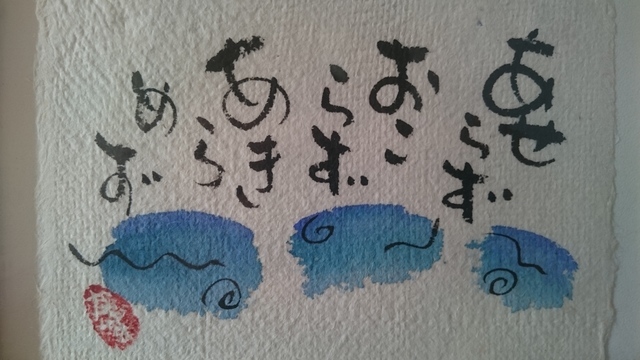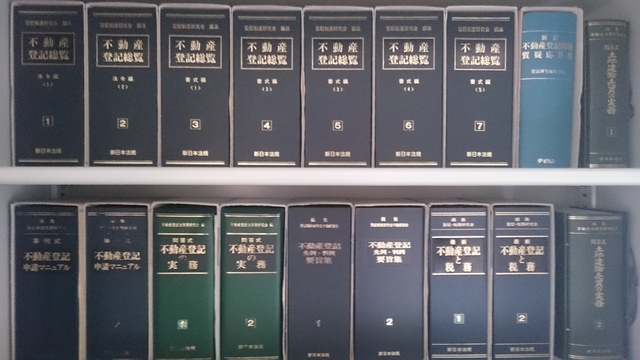0772-45-1686
本人訴訟支援、訴訟代理等(令和6年12月29日更新)

認定司法書士(特別研修を終了し法務大臣が認定した司法書士)は、簡易裁判所での訴訟代理業務を行うことができます。
それは珍しいものではなく、全司法書士の内78%(2023年4月1日現在)が認定司法書士です。
認定司法書士は訴額140万円を超えない額において、簡易裁判所における民事訴訟手続等を代理します。
また、140万円を超えない民事に関する紛争については、代理人として相手方と直接交渉し、裁判外の和解を成立させることもできます。
140万円を超える争いや、地方裁判所での訴訟、家庭裁判所での調停などでは、「書類作成業務」と呼ばれる方法で、本人を支援しています。
書類作成業務とは、「最終的な意思決定は依頼者本人の意思に委ねながらも、依頼者の真意を把握し、その究極の趣旨に合致するように”法的判断”を加えて、当該事件を法律的に整理し、完備した書類を作成する業務。」です。
司法書士が、簡易裁判所での訴訟や調停の代理、(訴状や答弁書、家事調停申立書等)裁判所提出書類の作成代理や、裁判外での和解交渉代理など行っていることを、ご案内いたします。
簡易裁判所での訴訟代理業務
認定司法書士の簡易裁判所代理権とは

認定司法書士は*訴額140万円を超えない額において、簡易裁判所における民事訴訟手続等を代理します。
*訴額は請求金額や目的物の価額などにより算定されます。
「代理する」とは、弁護士と同じく、簡易裁判所で代理人となって活動できるということです。
それは、訴訟、少額訴訟、調停、支払督促という裁判手続きであり、
紛争の種類としては、次のようなものがあります。
①金銭請求(貸金・立替金・売買代金・給料・報酬・請負代金・修理代金・家賃・地代・敷金や保証金返還・損害賠償など)
②家賃、地代の改定請求
③建物、部屋の明渡請求
④土地、建物の登記請求
⑤クレジット・ローン問題
⑥その他
また、140万円を超えない民事に関する紛争については、代理人として相手方と直接交渉し、裁判外の和解を成立させることもできます。
司法書士が、簡易裁判所での訴訟や調停の代理、(訴状や答弁書、家事調停申立書等)裁判所提出書類の作成代理や、裁判外での和解交渉代理などを行っています。
少額訴訟とは

原則1回の審理で、直ちに判決が言い渡される裁判です。
訴額は60万円以下で、金銭請求に限ります。
証拠書類は揃っていて、証人も審理の日に間違いなく出廷してもらえる案件に限ります。
内容が複雑だと通常訴訟に移行する場合があります。
話し合いでは解決できないけど、長い時間をかけて裁判する気もない、というような場合に選択する手続です。
つまり、普段の生活で直面する、いわゆる「小さなトラブル」を裁判所で解決するためのメニューとご理解ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/index.html
裁判所ホームページ「これから少額訴訟を利用しようとする方へ」
支払督促とは

債務者が渋っているけど、事実上の圧力がかかれば債権回収できそうな場合に利用できる手続です。
例えば10万円の売掛債権があるような場合、特に証拠資料がなくても、相手方の住所地の簡易裁判所に「10万円払え」と申し立てることができます。
そうすると、受理した簡易裁判所は特に証拠調べなどすることなく「10万円払え」という支払督促を相手方に送ってくれるのです。
相手方への送達後2週間たっても異議がない場合には「仮執行宣言」の申請をします。
さらに2週間、相手方から異議の申し立てがなければ、支払督促が確定し「確定判決」と同じ効力が生じます。
異議期間中に相手方から異議が出れば、支払督促の申立の時に訴訟の提起があったものとして、通常訴訟に移行します。
「私は本気ですよ!」と、不誠実な相手方に伝えるために有効な手段だと思います。
ですが、異議が出た場合は訴訟に移行しますから、申し立ての時点で、その対応についても考えておく必要があります。
https://www.courts.go.jp/…/syurui…/minzi_04_02_13/index.html
裁判所ホームページ 「支払督促」
民事調停とは

民事調停とは簡易裁判所でおこなわれる「話し合い」です。
紛争当事者が納得できるまで話し合い、お互いに譲るべきところは譲って(互譲)紛争を解決する制度です。
原則、調停委員が2名立会い、双方の言い分を聴いて調整を行います。
裁判ではないけれども、裁判所でおこなう「話し合い」だとご理解ください。
相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所へ申し立てます。
簡易裁判所で行いますが、申し立てる金額は140万円を超えても構いません。
話し合いで円満に解決するための手段ですので、専門職の代理人が行う場合であっても、訴訟のような喧嘩腰の内容の申立書を提出するのは、間違った態度です。
(そもそも、相手をコテンパンに遣り込めて、気分をすっきりさせたいがために裁判所を利用するという「ただ感情的な動機」を、法律は予定していません。)
まずは、民事調停で予定されている紛争解決とは、互譲の精神に基づく、大人の解決方法だとご理解ください。
https://www.courts.go.jp/…/syurui…/minzi_04_02_10/index.html
裁判所ホームページ 「民事調停」
家庭裁判所での手続き
家事調停とは

家庭に関する紛争を自主的に解決するため、家庭裁判所で行う話し合いです。
家庭に関する紛争とは、夫婦間の「離婚」「婚姻費用」「未成熟子の親権や監護権」、相続人間の「遺産分割」に関するものなどがあります。
家事調停は、裁判官1人と家事調停委員2人が構成員となった「調停委員会」によっておこなわれるのが原則です。
調停委員は、当事者のどちらの味方でもなく、双方の言い分を聴きながら調整し、当事者を合意に導き、具体的に妥当な解決を図るために活動します。
申立人と相手方が、交互に30分くらいずつ、お話しするケースが多いと思います。
実際のところ、相手方には、裁判所から呼び出し状が来ますので「裁判沙汰にしやがって!」と憤るのもごもっともだとは思いますが、
調停は裁判ではなく、「家庭裁判所という場所で行う話し合い」だ、と知っていただければ、誤解は解けると感じます。
話し合いであり、申し立て方法も簡便なので、専門家の関与なしに、本人で手続きされる方も多くいらっしゃいます。
話し合いですから、訴訟のようにお互いを攻撃し合う場ではない、と知っていただきたいと思います。
話し合いですが、合意に達しますと「調停調書」が作成されますが、それは確定判決と同じ効力を持ちます(強制執行できます)。
何度も「話し合い」と申し上げるのは、裁判所が白黒つける場ではなく、当事者で自主的な解決を図る場であるからです。
裁判所が決めた事よりも、「自分たちで納得して決めた約束」の方が守られるものです。
身近な法律入門 子どものための面会交流
身近な法律入門 離婚調停ってなに?
家庭裁判所での書類作成業務

家庭裁判所では、「離婚調停」「遺産分割調停」等、家庭の問題が扱われています。
司法書士は、家庭裁判所での調停等では代理人になることはできませんが、「書類作成業務」を通して依頼者をフォローしています。
離婚や、遺産分割調停において、代理人(弁護士)を選任しないで、本人自ら調停に臨むことを希望される場合に、書類作成者として関与しています。
なお、厚生労働省の統計によると、Ⅰ年間当たりの離婚件数は、令和5年度では47万4717件です。
また、厚生労働省「令和5年度「離婚に関する統計」の概要」によれば、協議離婚が約87%、裁判離婚が約13%となっています。
そして、弁護士が関与せず本人等で対応した離婚調停は約40%あり、家庭裁判所での離婚調停は、当事者本人でなされているケースが結構多いのです。
なお、このデータには、司法書士が書類作成援助した件数は反映されておりません。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
厚生労働省 離婚に関する統計
身近な法律入門 離婚調停ってなに?
身近な法律入門 子どものための面会交流