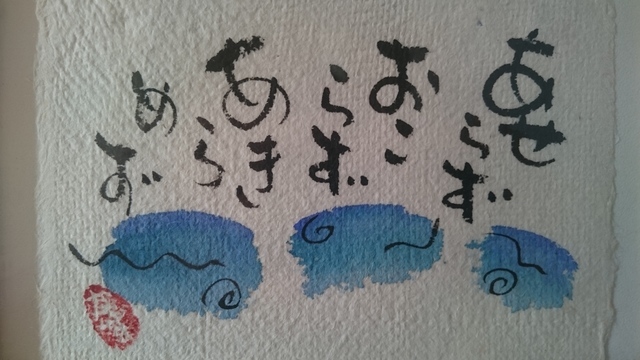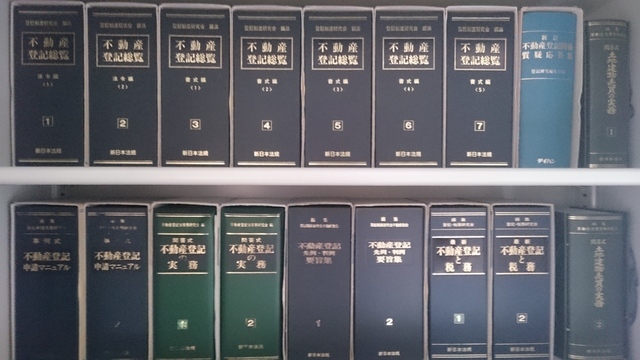0772-45-1686
遺言書作成(令和6年12月29日更新)

こちらでは遺言書作成について紹介いたします。
相続は遺言書の有無の確認から始まります。
遺言書は自分の死後に効力を発揮する最期の言葉です。残された者たちが無駄な争いをしないように残す、最後の優しさとも言えるでしょう。
遺言書がある場合、例えば不動産の名義変更では、遺産分割協議(相続人全員が実印を押印)を省略できます。
財産の多寡ではありません、ご自身も含め皆が充実した人生を送るための手紙と位置づけましょう。
身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ
身近な法律入門 相続法の改正について
身近な法律入門 終活ってなに?
身近な法律入門 遺言執行者とは
遺産承継業務
身近な法律入門 遺言書保管制度について
遺言書作成
遺言書を書いても財産を処分できるの?
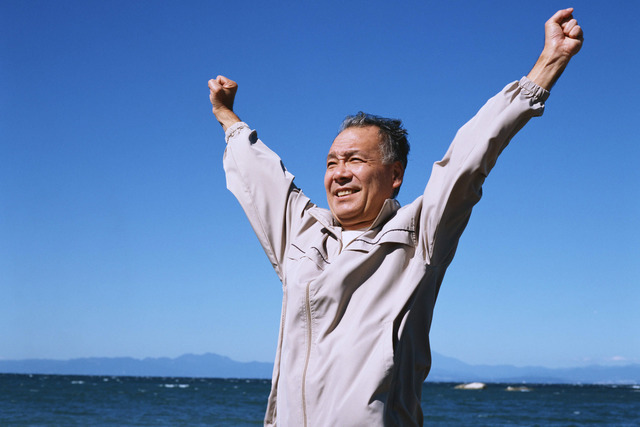
遺言書を書いたからといって何の制約もありません。
不動産を売却してもよいですし、預貯金が0円になってもかまいません。ご自分の財産なのですから自由に使えばよいのです。
なお、遺言書は何度でも書き換えることができます。ご自分のお気持ちを残してみませんか。
身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ
身近な法律入門 終活ってなに?
身近な法律入門 遺言書保管制度について
公正証書の遺言って、どうやってするんですか?

公証人に遺言したい内容を伝えて、公証人が遺言公正証書を作ります。
通常は予め遺言内容を文書にして公証人に交付し、内容を確認してもらいます。
その際に戸籍謄本等の必要書類も交付します。
公正証書遺言は公証人が作成してくれます。
遺言者は遺言の日に、その内容を公証人に口頭で告げて、公証人が遺言書を読み上げ、内容に間違いがなければ、その遺言書に「署名押印(実印)」を行います。
公証人という法律の専門家が関与するので間違いが少ない、その他多くのメリットがある遺言方法です。
私はこの方法をお勧めします。
身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ
身近な法律入門 終活ってなに?
身近な法律入門 遺言書保管制度について
遺言書が見つかりました
自筆の遺言書が見つかりましたが?
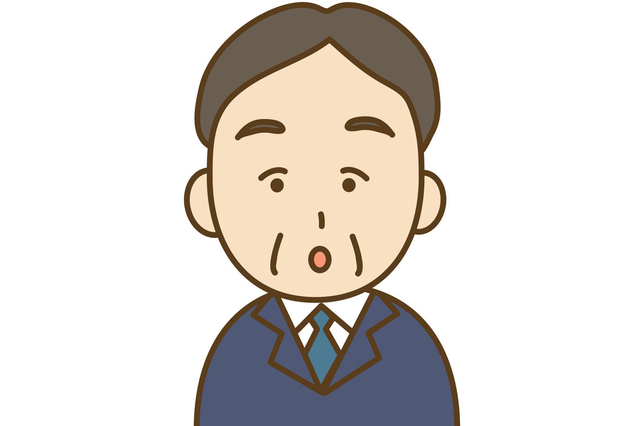
相続発生後、自筆の遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
検認とは家庭裁判所に相続人全員を呼んで(欠席者がいても差し支えありませんが、全ての相続人対して通知がなされます)、遺言書の存在を確認し、偽造変造を防ぐ手続きです。
この検認の手続きをしないと名義変更の手続きに使えないのが、自筆による遺言の欠点の一つです。(なお、公正証書による遺言の場合は検認が不要です。)
自筆による遺言の簡便さを選ぶか、公正証書による遺言の確実性を選ぶか。
まずは手書きで、考えを整理するのも良いかもしれませんね。
なお、法改正により、法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まります。
下記、相続法の改正をご参考ください。
身近な法律入門 相続法の改正について
身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ
身近な法律入門 遺言書保管制度について
遺言書が見つかりました。
相続人の方が先に亡くなっていますが?

遺言者が亡くなり遺言が見つかりました。
その遺言書には「長男Aに全財産を相続させる」と書いてあります。
ところがAは、遺言者よりも先に亡くなっていました。
その場合、Aの相続人はこの遺言により遺言者の全財産を相続できるでしょうか?
残念ながら、その遺言には効力がありません。
そんなお話を、身近な法律入門にご紹介しましたので、ご覧ください。
身近な法律入門 遺言書保管制度について
身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ
エンディングノートと遺言書
エンディングノートは書きましたが・・・?

ご自分が死期間近で意識不明に陥ったとき、蘇生して欲しいか、それともそのまま逝かせて欲しいか。
エンディングノートにはそんなことを書きますね。ちなみに私ならそのまま逝かせて欲しいですが。
遺言はエンディングノートとは少し違います。遺言は法律行為ですが、エンディングノートはお手紙とか覚書のようなものです。
ご自分の死後、財産を民法とは違うわけ方をすることができる崇高な行為です(例えば相続人以外の人にも財産を残せます)。
エンディングノートと遺言書をセットで作成しておく、それが大事な人を護ってあげることになるでしょう。
身近な法律入門 終活ってなに?
遺言執行者とは

せっかく遺言書を残しても、その内容が実現されなければ意味がありませんよね。
そこで、「遺言の内容を実現する事務を行う者」が必要となるのです。
その者のことを法律上「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」とよびます。
遺言執行者は遺言書の中で指定されます。
遺言書の中で指定がない場合は、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者の選任をしてもらうか、相続人全員で共同して遺言執行事務を履行することになります。
遺言者は、自分の遺言書の内容通りに、遺産分割をして欲しいと願っているはずです。
そんな遺言者の「最後の想い」を託された、「遺言執行者」のお話をしたいと思います。
遺言執行者は「遺言の内容を実現するため」(民法1012条第1項)活動します。
*つまり、必ずしも相続人の利益のために職務を行うものではありません。
遺言執行者がいる場合に、相続人が行った遺言の執行を妨げる行為は、原則「無効」となります(民法1013条第2項)。
また、遺言執行者がいる場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができます(民法第1012条第2項)。
遺言執行事務の大まかな流れですが、次のようになります。
①各相続人へ、遺言の内容と遺言執行者に就任した旨の通知
↓
②全財産の調査・把握をして財産目録を作成
↓
③遺言による財産の処分・承継に伴う登記・登録の名義変更や債権者・債務者に対する通知
↓
④対象財産の相続人等への引渡し
↓
⑤必要に応じ遺産の管理・保管など
遺言者は、自分の遺言書の内容通りに、遺産分割をして欲しいと願っているはずです。
そんな遺言者の「最後の想い」を託されたのが「遺言執行者」なのです。
*令和元年7月1日施行の民法により、遺言執行者に関する規定が詳細に整備されていますので、身近な法律入門 相続法の改正について をご覧ください。
身近な法律入門 相続法の改正について
身近な法律入門 相続手続きで困ったら
遺産承継業務