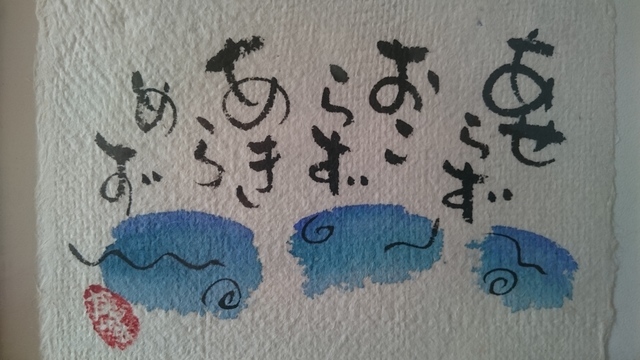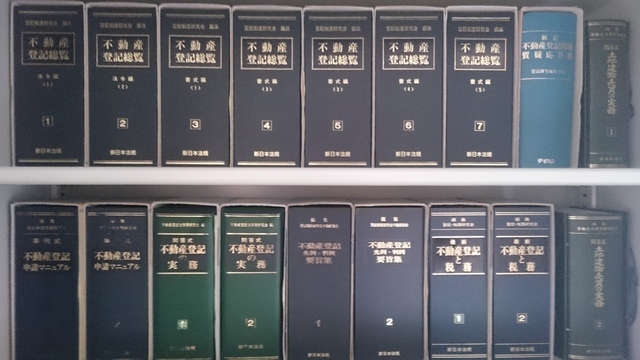0772-45-1686
高齢者だけでない消費者トラブル
(令和6年12月30日更新)
クーリング・オフとは

一人暮らしの高齢者が、親切な訪問販売業者を自宅に招き入れ、高級な羽毛布団を何組も購入している。
子供が実家に帰省した時に、部屋に山積みになっている布団を見て唖然とする。
年金暮らしの親なのに、クレジット契約を組まされて、多額の負債を負わされていた…。
これは消費者トラブルの典型例だと思いますが。
一人暮らしで話し相手のいない高齢者が、親切を装った訪問販売員を信用し(むしろ頼ってしまい)、消費者被害にあうケースは深刻です。
さらに、「認知症」の高齢者は「親切な訪問販業者」の「カモ」となる可能性が「より高い」という事は、みなさまも感覚でご理解いただけると思います。
本日は、あり得ない契約をしてしまった時の解除通知であり、今後度々ご案内する制度である「クーリング・オフ」を下記にご紹介します。
営業マンが、突然自宅を訪問して来て執拗に勧誘してきたり(訪問販売)、電話(電話勧誘販売)で巧みな話術を弄したりして、消費者は困惑しているままに、不要な物品購入などの契約をしてしまうことがあります。
特に、一人暮らしの高齢者がトラブルに巻き込まれるケースは社会問題となっています。
そこで、ご存知でしょうか?
訪問販売、電話勧誘販売に関しては、消費者から一定の期間内なら無条件で契約を解除できる制度があります。
これを「クーリング・オフ」と言います。
申込書や契約書(以下「法定書面」)を受け取った日を含めて、8日以内に解除通知を発すれば(発すればよく届いている必要はない)契約の解除ができます。
8日を過ぎてしまっている場合でもあきらめないでください。
法定書面の記載事項に不備がある場合(例えば、契約担当者の氏名の記載がない等)は、8日を過ぎていてもクーリング・オフはできるのです。
クーリングオフは「書面」で行う必要があります。
後日紛争とならないように、内容証明郵便で送付することをお勧めします。
契約が解除されますと、業者は受け取っていた代金を返還しなければなりません。
一方、消費者はその商品を既に使っていた場合でも、その費用を業者へ支払う必要はありません。
事業者は、消費者に対して契約解除に伴う損害賠償や違約金の請求はできませんし、商品の返品費用も事業者の負担となります(消費者は、事業者がとりに来るまで商品を保管していればよい。)。
クーリング・オフの文書は簡単な内容です。
でも、消費者被害回復には強力な武器なのです。
消費者トラブルとは
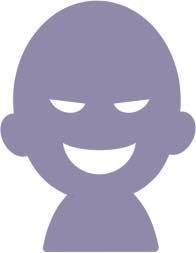
ワンクリック詐欺・サクラサイト詐欺・モニター商法・原野商法・マルチ商法・点検商法・次々販売・かたり商法・催眠商法・送り付け商法・振り込め詐欺…etc…。
みなさまは、その中でいくつご存知ですか?
若者も消費者トラブルに遭いますよね。
スマホで無料サンプル等を閲覧していると、突然「会員登録ありがとうございます。あなたの情報を登録しました。約定の登録料をお支払いください。」等と表示が出て(ワンクリック詐欺)、慌ててしまったことはありませんか?
若者ですら、この程度の表示に慌てて返信して詐欺に遭っていますよね。
では、高齢者の事情はどうでしょう?
高齢者には若者よりも消費者被害に遭いやすい理由があります。
①家にいることが多く、「訪問販売」や「電話勧誘販売」の被害を受けやすい。
②老後の蓄えがあり、それを狙われやすい。
③健康や生活への不安を抱いており、そこに付け込まれる。
④高齢になると若い頃と比べて認知能力や判断能力が落ちている。
⑤高齢者の一人暮らしは多く、孤立や孤独による淋しさに付け込まれる。
私達に必要なことは「騙されないための教育と学び」であり、そして高齢者には「身近な人たちによる見守り」を追加する必要があると感じています。
身近な法律入門 成年後見制度とは
ワンクリック詐欺について
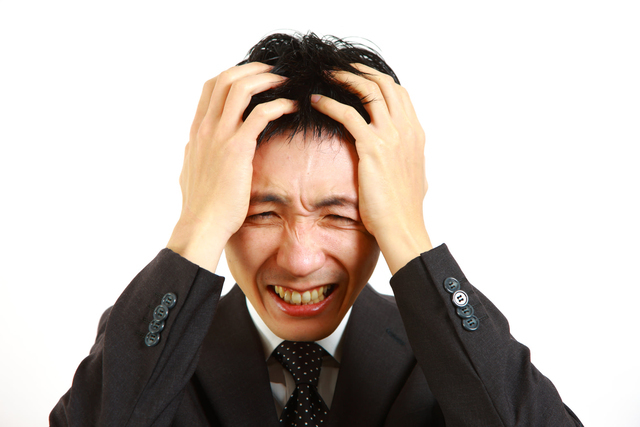
<事例>
インターネットで検索を続けていると、突然「会員登録を受け付けました。登録料は3万円です。この案内に覚えがない場合は、〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇までご連絡ください。」とのメッセージが表示されました。
その表示には自分のプロバイダ情報や、住んでいる市町村まで記載されているので、自分の個人情報を知られてしまったと思いました。
会員登録した覚えはないので、メッセージにあった連絡先に連絡してしまいました…。
これは、高齢者だけではなく、若者も経験しそうな場面ですね。
契約の成立には「申込」と「承諾」という、当事者双方の意思の合致が必要です。
この事例の場合、「申込」の意思のない「ワンクリック」により契約は成立していません。
つまり、登録料を支払う必要はありません。
これは「ワンクリック詐欺」という「詐欺」なのです。
ワンクリック詐欺では、消費者の側から業者に連絡をさせ、個人情報を聞き出すというのが手口です。
つまり、業者はパソコンやスマートフォンの登録情報から個人情報を得ることができないのです。
あなたの個人情報は知られていませんので、
業者からのメッセージに慌てて連絡してはいけません。
通信販売のトラブルについて

<事例>
自宅にダイエット用サプリメントが大量に届き、高額な代金が請求されました。
母に確認すると「絶対にやせるって書いてあるし、あなたがやせたいって言ってたから…。」と言っています。
親心は有難いのですが、母は騙されてるんじゃないかと思うんです…。
解約して返品できるでしょうか?
高齢者にとっても通信販売は、出掛けずに購入できて便利なので利用しますね。
ですが、その広告の表示が「ウソ」であることもあり得ます。
返品の方法ですが、通信販売には「クーリング・オフ」の制度がありません。
それは、通信販売は、訪問販売や電話勧誘販売のように、突然の勧誘で不当な圧力を受けて混乱して契約をすることがないからです。
返品方法としては
①商品の広告にある「返品特約」を確認する。
②返品方法の表示がない場合は「特定商取引法」による返品権を行使する。
*商品の引渡し日から8日以内に契約解除が必要
*解除の通知が相手方に届かなければならない
(クーリング・オフは発送すればよいが、通信販売ではできない。)
*商品の返送料は消費者の負担となる
(クーリング・オフは業者の負担にできるが、通信販売ではできない。)
③消費者契約法による「不実告知」を主張して解除する。
④消費者契約法による「断定的判断の提供」を主張して解除する。
*不確実な事項に関して、「絶対にやせる」という「断定的な判断」を提供し、消費者に誤認を生じさせている。
いずれかの主張をし、配達証明付内容証明郵便を発送して解除通知をし、別便で商品を返送することになると思います。
まったくもって、面倒ですよね。
だから、騙されないようにしないといけませんよね。
かたり商法とは

事例
「消防署の関係で来ました。消防法が改正されたので地域を巡回させていただいております。」
と業者が訪問して来ました。
「規定の消火器を備えないと罰則もありますが、ご準備は済まされましたか?」
等と言われたので、高額の消火器を購入してしまいました。
後で気付いたのですが、
消防署って消火器を売りに来るのでしょうか?
このように「水道局から来ました。」「NTT関係の者です。」「消防署の関係で来ました。」と公共機関や大手企業を装って商品を売りつける商法を「かたり商法」とよびます。
あたかも公共機関等から業務で来たかように「虚偽の事実を告知して販売をした」場合は、消費者契約法で契約の取消しができます。
また、訪問販売ですから、以前ご案内した「クーリング・オフ」の要件にあえば、何らの理由も必要とせず、かつ無条件で契約の解除ができます。
しかし、被害に遭った上に、さらに損害の回復のためにいろいろと手続きするのは苦痛ですよね。
つまり、騙されないようにすれば良いのです。
公共機関が物品販売をするはずがないと、知りましょう。
特に高齢の一人暮らしの方などが騙されないように、地域で見守ってあげてください。
身近な法律入門 成年後見制度とは
送りつけ商法(ネガティブ・オプション)とは

事例
自宅に小包が届き、開封してみると、マスク数枚とアルコール除菌剤と書いてあるボトルが1本入っていました。
送り状に「厚生労働省 医療支援基金係」と書いてあるので電話してみたところ、
「政府の無償配布数を超えるマスクと除菌剤をご希望されたのでお送りしました。」
「もう、商品を開封したんですよね?」
と言われ、医療機関への寄付金を含めて3万円を振り込むように言われました。
同居している認知症の父が発注したのかもしれません。
振り込まないといけないのでしょうか?
ご回答
このように、消費者が何も注文していないのに、商品を送りつけてくることを、ネガティブ・オプションといいます。
売買契約の成立には「申込」と「承諾」が必要でしたね。
ネガティブ・オプションの場合は、業者から商品を買ってくれという「申込」を行っていることになりますが、勝手に商品を送ってきたわけですから、あなたに「承諾」をする義務はありません。
ただ、送られてきた商品を使用してしまった場合は、購入を「承諾」したと評価されるので注意が必要です。
この事例の場合は、小包を開封しただけですから、商品を使用したことにはなりません。
勝手に商品を送りつけてきて、こんな迷惑なことはありませんよね。
だから、そのために法律(特定商取引法)で「商品が送られてきてから14日経過した日」までに、あなたが「承諾」せず、かつ、業者がその商品を引き取らないときは、その商品を処分しても良いことになっています。
つまり、14日経過後はそのマスクを使っても良いのです。
*ただし、商品が届いた日を証明できるように、送り状を残しておく等して証拠を保全しておくことをお勧めします。
この手の詐欺は、受け取りを拒否するのが最善の対応ですが、政府の施策に便乗して、送り状に「マスク等」と書いてあったら受け取ってしまうのはやむを得ません。
公共機関が物品販売をするはずがないと、知りましょう。
そして、特に高齢の一人暮らしの方などが騙されないように、地域で見守ってあげてください。
身近な法律入門 成年後見制度とは