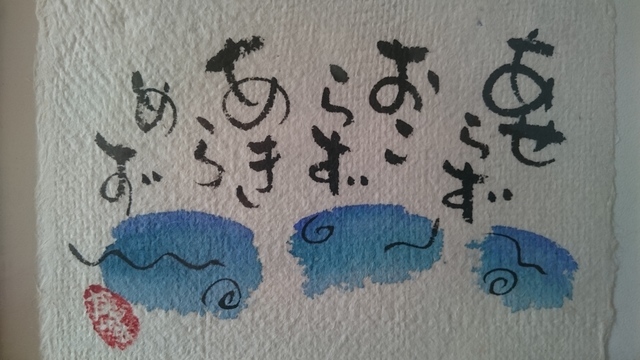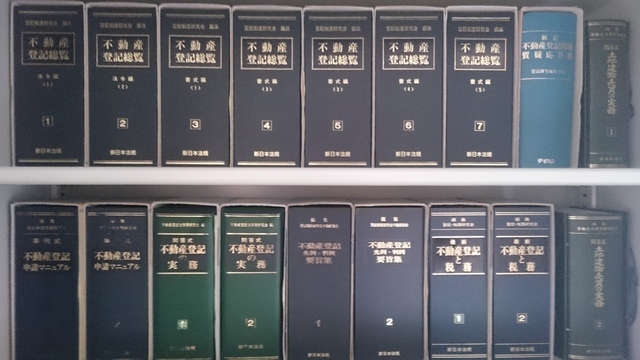0772-45-1686
遺言執行者とは(令和6年12月30日更新)
遺言執行者とは

せっかく遺言書を残しても、その内容が実現されなければ意味がありませんよね。
そこで、「遺言の内容を実現する事務を行う者」が必要となるのです。
その者のことを法律上「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」とよびます。
遺言執行者は遺言書の中で指定されます。
遺言書の中で指定がない場合は、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者の選任をしてもらうか、相続人全員で共同して遺言執行事務を履行することになります。
遺言者は、自分の遺言書の内容通りに、遺産分割をして欲しいと願っているはずです。
そんな遺言者の「最後の想い」を託された、「遺言執行者」のお話をしたいと思います。
遺言執行者は「遺言の内容を実現するため」(民法1012条第1項)活動します。
*つまり、必ずしも相続人の利益のために職務を行うものではありません。
遺言執行者がいる場合に、相続人が行った遺言の執行を妨げる行為は、原則「無効」となります(民法1013条第2項)。
また、遺言執行者がいる場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができます(民法第1012条第2項)。
遺言執行事務の大まかな流れですが、次のようになります。
①各相続人へ、遺言の内容と遺言執行者に就任した旨の通知
↓
②全財産の調査・把握をして財産目録を作成
↓
③遺言による財産の処分・承継に伴う登記・登録の名義変更や債権者・債務者に対する通知
↓
④対象財産の相続人等への引渡し
↓
⑤必要に応じ遺産の管理・保管など
遺言者は、自分の遺言書の内容通りに、遺産分割をして欲しいと願っているはずです。
そんな遺言者の「最後の想い」を託されたのが「遺言執行者」なのです。
*令和元年7月1日施行の民法により、遺言執行者に関する規定が詳細に整備されています。
身近な法律入門 相続法の改正について
身近な法律入門 相続手続きで困ったら
遺言書作成