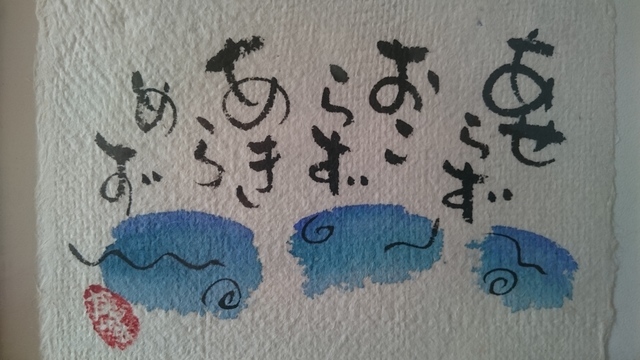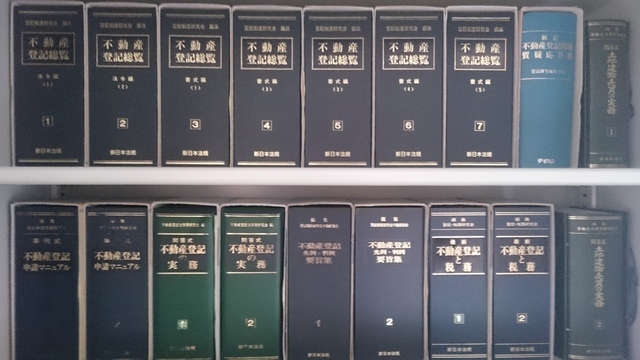0772-45-1686
離婚調停ってなに?(令和6年12月30日更新)
離婚調停とは

我が国の離婚方法には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」を基本として、「和解離婚」「認諾離婚」「審判離婚」があります。
協議離婚とは、夫婦で役所に離婚届を出すだけで離婚できる手続きで、この離婚方法を採用しているのは、先進国では日本だけです(他の国ではこんなに簡単には離婚できません)。
日本では離婚の約9割がこの協議離婚であるとされています。
残りの約1割が家庭裁判所の手続きを経ての離婚となります。
いきなり「離婚審判」や「離婚訴訟」を起こしても「離婚調停」に付されます。
これを「調停前置主義」といいます。
家庭に関することは、話し合いで柔軟に解決する方が当事者のためになることが多いので、訴訟の前に話し合いの機会を設けるという趣旨です。
離婚調停は、正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれます。
夫婦関係調整調停には、
絶対に離婚したい!という「離婚調停」。
別居しながら他の取り決めを求める「別居調停」。
夫婦円満にやり直すことを前提に、その際の取り決めを求める「円満調停」があります。
あ、円満調停ってご存知でしたか?
ぜひ利用して欲しいですね。
ところで、法律の話ではありませんが、
愛し合って結婚したはずの夫婦が、なぜ憎み合って離婚するのでしょうか?
「言った」「言わない」で徹底的にもめるのは、世間で「よくある」つまらない争いです。
しかし夫婦間では、
妻は「何度も言ったのに」と言い、夫は「聞いていない」という現象が「よくある」不仲の原因なのです。
行動心理学上、男性は主に情報伝達が目的で話をするが、女性は主に感情を伝え、共感を得ることが目的で話をする、と説明されることがあります。
つまり、話す目的が違うから、男女間ではコミュニケーションがとりにくいのだという話です。
この男と女の永遠の謎を、
説明できる方がいらっしゃれば、ぜひ教えて頂きたいと思います。
身近な法律入門 子どものための面会交流
本人訴訟支援、訴訟代理等
離婚調停における協議のメニューについて
離婚調停は話し合い

いわゆる離婚調停でおこなわれる「話し合い」には、様々な論点(調停は話し合いなので「争点」とは言いたくありません。)があります。
例えば、「未成熟子の親権や監護権」「面会交流」「養育費」「婚姻費用」「財産分与」「年金分割」「慰謝料」等…。
それらの論点を、離婚調停の中で同時に話し合いをして、合意ができれば(問題の一回的解決)望ましいことは言うまでもありません。
しかし、双方とも離婚は合意していて、かつ全体的な解決を望んでいるのに、離婚の付随論点でお互いに譲らないことがあります。
そこには「見えない動機」の存在がうかがえます。
例えばこんな場合
お互い離婚はしたいけれども「親権」は譲らないと言って、話し合いが硬直してしまった状況には、
こんな「見えない動機」があるかもしれません。
①表面的には離婚に同意しているけれども、本心は離婚したくないと思っている。
②相手方の言いなりになりたくないという心情的理由がある。
③子供との関係が途絶えることを懸念している。
④家や姓の維持にこだわっている。
⑤金銭面などの離婚条件を有利に進めたいと考えている。
⑥親族(子にとっては祖父母)の強い意向がある。
これは、当事者自身が自覚しているときと、していないときがあります。
その相手方の動機を見極める努力をして、
①や②であれば心情的な調整に気を配ったり、③であれば面会交流の充実を提案したり、④や⑤であれば子供の利益を第一に話し合いをしましょうと提案してみたり、⑥であれば子供の親は自分たちなのだと気づかせる等、
当事者にも穏当なアクションの仕方があると思います。
調停の場では、決して喧嘩腰に(争う姿勢で)主張するのではなく(相手の悪口ばかり言わず)、
相手の心情的な満足が問題解決には特効薬なのだという事を理解して(相手を叩きのめしてやろうなんて思わないで)、話し合いをすれば、
将来のあなたの人生にとっても、有益な解決方法が見つかると思います。
万一、あなたが依頼した弁護士さんが「喧嘩常套」であったなら、
「私は穏当に解決できるならばそうして欲しい。」と伝えてください。
調停が成立しなければ、その後は、審判や訴訟でいくらでも「喧嘩」できます。
「元夫婦」という関係も、良好であることに越したことはありませんから。
身近な法律入門 子どものための面会交流
本人訴訟支援、訴訟代理等
離婚調停における協議のメニューについて
調停に代わる審判とは

「調停に代わる審判」は、離婚調停における「面会交流」や「養育費」に関する事件、遺産分割調停等において、家庭裁判所が活用することがある手続です。
それは、次のような状態の時に有用であるとされています。
① 調停でほとんど合意できているのに、当事者の一方が裁判所に出頭することが困難な事案。
② 相手方が調停に一切出席せず、今後の出頭や対応も見込まれない事案。
③ 例えば養育費額について、わずかな差であるのに、当事者が心情的に合意できないといった事案等。
上記の状態の場合に、裁判所が調停手続きの中で「審判」として合意案を示します。
そして、双方から異議が出なければ、その内容で審判が確定し、合意が成立したこととする手続です。
異議が出たとしても、通常の審判手続きに自動的に移行する種類の手続きもあります。
家庭裁判所が「ちょっと背中を押す」感覚でしょうか。
「調停に代わる審判」を活用して、迅速・適正かつ柔軟な解決の実現が図られています。
身近な法律入門 子どものための面会交流
本人訴訟支援、訴訟代理等
離婚調停における協議のメニューについて
離婚を決める前に、それから

【離婚を決める前に】*DV事案を除きます。
本当に離婚という手段しか残っていないのでしょうか?
もう一度、その選択を疑ってみる価値はあるかもしれません。
離婚を応援する友人の意見は参考程度にしましょう。
その友人が離婚後も親身に話を聴いてくれるとは限りません。
離婚後に困ってその友人に再度相談したら「あなたが決めた事でしょ?」なんて、冷たく言われるかもしれません。
【離婚を決意したら】
離婚しか方法がなかったとしても、強引に破壊してはいけません。
ものごとを冷静に進めましょう。
あなたは人生の再スタートへの思いで頭がいっぱいですが、パートナーやその親族にとっても人生の再スタートとなるのです。
離婚すると決めたならば、きれいに別れることを考えましょう。
パートナーやその親族の悪口は問題をこじらせるだけです。
ここでも色々聞いてくれる友人は心強く感じますが、それは、ただその友人が、あなたの家庭問題を興味本位で、色々聞きたいだけなのかもしれません。
問題がこじれる原因に、離婚問題に素人である「友人の意見」がよくあるのです。
【子どもたちへの配慮】
あなたはパートナーとの関係を、養育費のやり取りだけで済ませたいのでしょう。
でも、子どもと別居親の交流の維持に努めましょう。
子どもたちへは、
「お父さんとお母さんは離婚するけれども、あなたたちにとって、いつまでもお父さんとお母さんだから、将来のことは心配しなくても大丈夫だよ。」
と約束してあげてください。
そして、その通りにしてあげてください。
【離婚した方の友人へのお願い】
「なんで離婚したん?」と簡単に聞かないでください。
離婚した方は、その質問を何十回も聞かれて何十回も答えています。
それが離婚後10年たっていようが、本人にとっては決して楽しい話題ではないと思いますよ。
身近な法律入門 子どものための面会交流
本人訴訟支援、訴訟代理等
離婚調停における協議のメニューについて