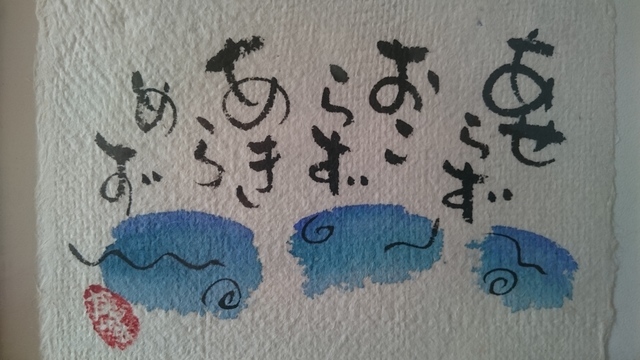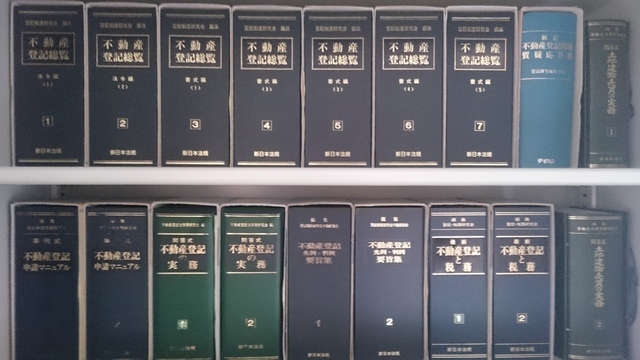0772-45-1686
民事信託(家族信託)について
(令和6年12月30日更新)
民事信託(家族信託)の仕組みと事例1
私が死んだ後、障害のあるわが子のことが心配という事例
信託は、「信頼できる人」に財産の名義を移してその財産の管理や活用、そして処分を託す制度です。
家族のために、そして、その「信頼できる人」の役割を「家族」にお願いしたスキームを「家族信託」と呼ぶことがありますが、以下家族信託を含め、表記を「民事信託」で統一いたします。
私は「高齢者や障害のある人の生活の支援のために活用する制度(福祉型民事信託)」としてご紹介いたします。
信託の主人公は3者あります。
「委託者」(信託を設定し財産を提供する人)、「受託者」(設定された信託内容の通りに信託事務を担う人)そして「受益者」(信託によって利益を得る人)です。
例えば、こんな場面を想像してください。
<障害のあるお子様を持つお母さんが、自分の亡き後の子どもの生活を心配している。>
お母さん(委託者)が、信頼している甥っ子(受託者)にお願いして信託契約(信託行為)をする。
その信託契約は、障害のある我が子(受益者)の生活支援のために信託財産を活用するようにとする内容で、お母さんの財産の一部(預金等)を、信託財産として甥っ子に託す。
そして、その託した財産は、信託行為の目的通りにしか利用されない仕組みがある。
というものです。
信託は「信託目的」(例えば、受益者の安定した生活の支援と福祉の確保、等)に定めたとおりに履行されます。
民事信託の方法は①契約②遺言③宣言の3つがあります。
*私は上記いずれの場合も、公証人が作成する「公正証書」で行うべきだと考えています。
そして、委託者が信託した財産は、名義は受託者になりますが、その性質は、「誰のものでもない財産」になります(法律的にそのように構成されます)。
よって、信託した財産は、委託者や受託者が破産しても破産財団には組み込まれないし(倒産隔離機能)、委託者や受託者が死亡しても相続財産にはなりません。
つまり、委託者が信託行為をした通りに(その後、委託者が倒産しても死亡しても。)、受益者のために運用され続ける財産となります。
例えば個人事業で成功している方(委託者)が、自分の障害のある子ども(受益者)のために信託をしておく。
そうすると、万一委託者が後年破産したとしても、昔に信託した財産は差し押さえを受けることなく、子ども(受託者)のために運用され続けるということです。
民事信託支援業務
民事信託の事例2
先妻との子と後妻の関係が悪くて心配という事例

<遺言ではできないけど、民事信託なら>
事例
Aさんは自分名義の自宅で後妻のBさんと暮らしています。
Aさんには先妻との子であるCさんがいます。
BさんとCさんは折り合いが悪いようです。
Aさんは自分の死後もBさんにこの自宅で生活できるようにしてあげたい。
でも、Bさんの死後は実子であるCさんにこの自宅を相続して欲しいと思っています。
どうしたら良いでしょうか?
先ず考えるのが遺言ですね。
でも遺言では「Bに遺贈する」又は「Cに相続させる」としかできません。
Bさんに遺贈するとBさんの所有になりますから、Bさんの相続人でないCさんは相続できなくなります。
では、Cさんに相続させたらいいか?というと、自分の死後、CさんによってBさんが家を追い出されてしまうかもしれません。
遺言ではAさんの希望は叶えられないかもしれません。
では、信託ならどうでしょうか。
Aさんが、この自宅には自分が亡くなった後もBさんが住めるようにして欲しい、でもBさんが死んだら、この自宅はCさんの物にして欲しい。
民事信託(このケースは後継ぎ遺贈型受益者連続信託といいます)なら、そんなAさんの希望が叶えられます。
民事信託を、そんな家族の事情に合わせた使い方でご提案したいと思います。
民事信託支援業務
民事信託の事例3
家族同様のペットのことが心配という事例
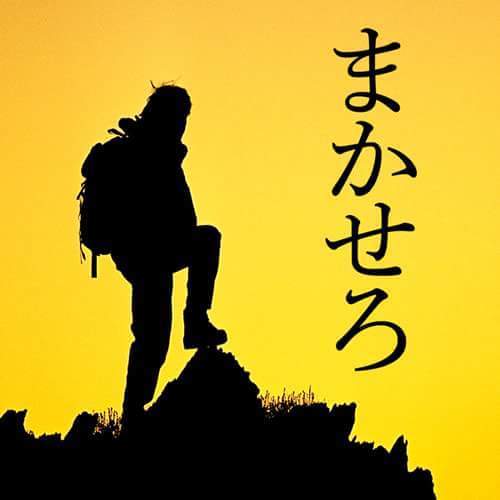
事例
Aさんは一人暮らしで、自分が亡くなった後、わん吉(愛犬)がどうなるのか心配しています。
さて、どのような方法が考えられるでしょうか。
今までされていた方法は「負担付遺贈」という方法です。
それは、「私の遺産をBにあげるけど、わん吉(愛犬)の世話をしてくれることが条件です。」という条件付きの遺言です。
この方法は、遺産を渡しても、Bが必ずわん吉を最後まで世話してくれるか、ということは保証されません。
そこで信託を利用します。
Aさん(委託者)が自分の死後、わん吉(ペット)の世話をしてくれる人を受益者とし、わん吉(ペット)の世話にかかわる費用についての金銭管理を引き受けてくれる人を受託者とする信託をします。
毎月、(金銭管理をしている)受託者が(ペットを世話している)受益者に飼育料を支払うという内容の信託です。
こうすれば、わん吉が飼育放棄されることはなさそうですね。
そんな家族同様のペットの将来のことまでも、お願いできるのが「民事信託」という仕組みなのです。
民事信託支援業務
民事信託の事例4
自宅が空き家のまま放置されないように
事例
Aさんは一人暮らしで、自分が施設に入ってしまったら、自宅は空き家になってしまいます。
もしAさんが認知症になれば、生前に自宅を処分できなくなることもあります。
この家が空き家のまま放置され、やがて廃墟となり、近隣の迷惑になることが心配です。
さて、どのような方法が考えられるでしょうか。
その自宅を信託財産として、親族を受託者として、信託契約をする方法でAさんのご希望を叶えることができそうです。
Aさん自身を受益者とし、受益権の内容は ①自宅不動産に居住する権利と ②生活に必要な費用を受け取る権利を定めておきます。
施設入所までは今までの生活ができますし、施設入所後は不動産の賃貸や売却をしてもらい、その利益から施設費などの給付を受けるスキームです。
こうすれば、Aさんが施設での生活に困ることはなく、自宅が放置されることもなさそうですね。
そんな、「空き家空き地問題」にも対応できるのが「民事信託」という仕組みなのです。
民事信託支援業務
身近な法律入門 空き家空き地問題って何?
民事信託と任意後見制度の併用について

事例
相談者Xの妻は既に死亡し、実子Yは知的障害者です。
XはZと再婚し、仲睦まじく生活しています。
なお、Zには連れ子のBがいますが、Bは既に独立しています。
Xの資産は自宅と預金1,000万円です。
XはZと余生を過ごしたいと思っていますが、Zに財産管理をさせるつもりはなく、遺産はYに承継させたいと考えています。
Xは、信頼できる甥Aと任意後見契約をして任せようと思っていますが、それだけでXの思いは実現できるでしょうか?
検討
1.成年後見制度は本人の意思能力が衰えた時に、本人の財産管理と身上保護を行う制度です。
本人の「全財産を」管理し、「本人のために」利用することになります。
つまり、成年後見制度では財産を本人以外の親族等のために使うことが、原則できなくなります。
2.一方 民事信託は、予め信託した特定の財産を(全財産ではない)、信託目的に従って利用するものです。
よって、(妻Zの存命中はZが自宅を利用してください等)家族のために使うことも可能です。
しかし、成年後見制度ならできる身上保護(本人の入院契約や、施設入所契約等、身の回りの契約等)はできません。
そこで、民事信託と任意後見契約を両方利用することにより、両制度の利点を活用できるのです。
本ケースですと、
①Xは甥Aを受託者とする信託契約をし、自分Xと妻Zが生きている間は自宅はXとZが使うけれども、二人とも死んだあとは実子Yの物にすることができます。
現金の一部を信託し、Yの療養看護費用に必要な支払いに充ててもらうことができます。
②Xは甥Aと任意後見契約をし、Xが認知症により施設などへの入所が必要になった時の対応をお願いできます。
①で信託した以外の全財産は、Xの療養看護費用等、存命中はXのためだけに使用されます。
「家族難民」「パラサイト・シングル」等と称される「無縁社会」が訪れました。
既に生じている深刻な問題に対応しなければなりません。
民事信託、成年後見制度、遺言、死後事務委任契約の4制度を駆使した終活を必要とする時代が到来しています。
身近な法律入門 成年後見制度とは
成年後見業務
身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ
身近な法律入門 終活ってなに?
民事信託支援業務