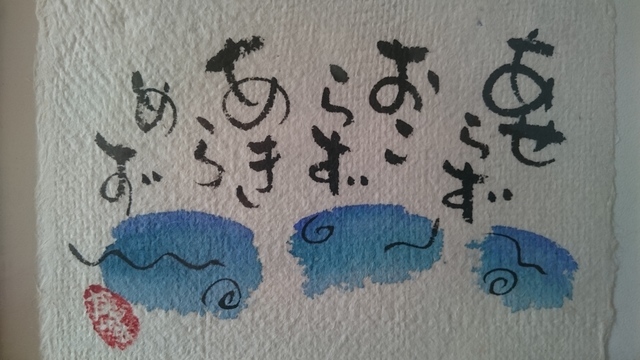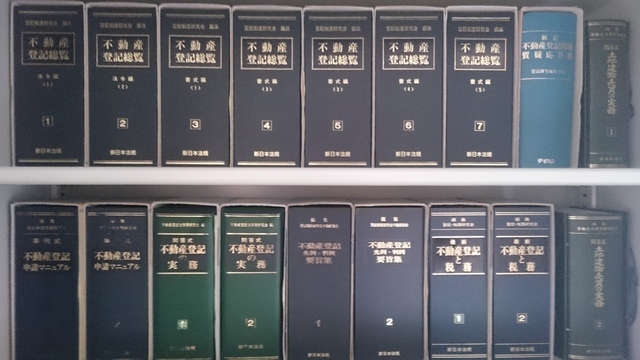0772-45-1686
遺言にまつわるエトセトラ(令和6年12月1日更新)

私には財産はないから。
子供たちはみんな仲良いから。
なんだか難しそう・・・。
遺言を書かない大きな理由はそんなところでしょうか。
少しでもたくさん欲しくなるのが人情。
今、子供たちがうまくいっているのは、あなたの存在があるからかもしれません。
あなたの亡き後、家族間の不要な争いを予防するために。
実は、紙とボールペン、認印があれば遺言は書けます。
それで防げる相続争いがあるとしたら。
たとえば、特定の誰かに不動産を譲りたい場合、遺言書があれば、相続人全員から実印をもらわなくても名義変更が可能です。
あなたの最期の言葉を残しませんか?
遺言書作成
終活ってなに?
相続法の改正について
遺言書保管制度について
遺言執行者とは
相続人以外にも財産を残したい

私は長男夫婦と同居しています。
長男の妻が私に良く尽くしてくれましたので、財産を残したいと思います。
方法はありますか?
遺言に書くことによって可能です。
遺言書がない場合、法定相続人のみが相続しますので、相続人でない長男の妻には財産を残すことは難しいのです。(注)
しかし、遺言により様々な財産分けが可能となります。
お世話になった人や施設などに遺贈(いぞう)することもできます。
(注)令和元年7月1日以降に開始した相続について、被相続人(亡くなった方)の相続人ではない親族(ex.長男の妻等)に、「特別寄与料」の請求を認める制度ができました(民法第1050条)。
遺言書作成
家族信託(民事信託)について
全財産を長男に相続させたい

私は先祖代々続く農家です。
子供は3人います。
今は長男が跡取りとして家業を切り盛りしてくれています。
私の財産はほとんどが農地です。
できれば頑張っている長男に全財産を相続させたいと考えています。
そんな遺言を書くことは可能ですか?
一人の相続人に全財産を相続させるという内容の遺言も作成可能です。
しかし遺留分(いりゅうぶん)といって他の相続人にも一定の相続権が残っています。
つまり、他の相続人は、ご長男に「遺留分侵害額に相当する現金を払え」、と主張することができるのです。
よって、一人の相続人に全財産を相続させるという遺言は、相続もめの原因となりますので、あまりお勧めできません。
家業のためどうしても必要であるならば、あなたのご生前にすべての相続人を説得しておくなどの配慮が必要でしょう。
できれば全員が納得できるような内容の遺言を残してあげてください。
終活ってなに?
家族信託(民事信託)について
遺言書作成
相続法の改正について
遺言書保管制度について
遺言執行者とは
遺言は簡単

遺言書には様々な種類があります。
一番お金がかからないのが手書きの遺言、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)です。
実は、大きな文具店には遺言書作成キットが売っています。
遺言は何度でも書き直しできますから、最初はこれでもいいと思います。
ですが、ワープロで作ったら無効、日付が抜けていたら無効など細かい要件があります。
不備があった場合や改ざん、破棄される恐れ、発見してもらえない可能性、相続発生後に家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要などデメリットがあります。
*遺産「目録」はワープロなどでも良い(平成31年1月13日以降に作成された遺言)、遺言書の遺言書保管所(法務局)での保管制度(令和2年7月10日施行)という法改正がなされています。
私がお勧めするのは公証人の面前で行う遺言、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)です。
数万円の公証人費用が要ること、遺言の証人が二人必要なことがデメリットです。
しかし、公証人という専門家が遺言内容をチェックしますので不備がない。
遺言書の原本が公証人役場に保管されるため紛失の心配がない。
全国の公証人役場から遺言書の存在を検索できる。
家庭裁判所の検認手続きが不要。など重要なメリットがあります。
あなたの最期の言葉を残しませんか?
遺言書作成
遺言にまつわるエトセトラ
相続法の改正について
遺言書保管制度について
遺言執行者とは
公正証書の遺言とは

*公証人(下記注)に遺言したい内容を伝えて、公証人が遺言公正証書を作ります。
実務では予め遺言内容を文書にして公証人に交付し、内容を確認してもらいます。
その際に戸籍謄本等の必要書類も交付します。
公正証書遺言は公証人が作成してくれます。
遺言者は遺言の日に、その内容を公証人に口頭で告げます。そして、公証人が遺言書を読み上げ、内容に間違いがなければ、その遺言書に「署名押印(実印)」を行います。
公証人という法律の専門家が関与するので間違いが少ない、その他多くのメリット(下記の通り)がある遺言方法です。
私はこの方法をお勧めします。
その際に、遺言の証人が2名必要となります。
遺言の証人は、相続を受けるものであってはなりませんので、友人や専門家にお願いすることが多いと思います。
公正証書による遺言のメリットは
①法律の専門家である公証人のチェックが入っているので不備が少ない。
②自筆証書遺言(手書きでかつ法務局に保管していないもの)のように、遺言者の死後に家庭裁判所の検認手続をしなくても良い。
③遺言者が120歳になるまで、公証人役場に遺言書が保管される。
④遺言書があるかどうかを、相続人が検索できる仕組みがある。
(注)*公証人とは法務大臣に任命された公務員で、裁判官や検察官、法務局長を経験した方が多いようです。
なお、公証人役場は各地の法務局の管轄に属し、全国に約300か所あります。
http://www.koshonin.gr.jp/system/s02/s02_02
日本公証人連合会ホームページ
遺言書作成
遺言にまつわるエトセトラ
相続法の改正について
遺言書保管制度について
遺言執行者とは
残念な遺言書もあります

遺言者の死後、相談を受けた案件です。
公正証書遺言でした。
遺言があったのに、残念ながら熾烈な相続争いとなりました。
結局、遺産分割調停は不成立となり、訴訟になりました。
事例
遺言者が亡くなり遺言書が見つかりました。
その遺言書には「長男Aに全財産を相続させる」と書いてあります。
ところがAは、遺言者よりも先に亡くなっていました。
その場合、Aの相続人はこの遺言により遺言者の全財産を相続できるでしょうか?
残念ながら、その遺言には効力がありません。
なぜならば、相続を受けるはずのAが存在しないからです。
結論としては、遺言者の相続人全員が法定相続人となり、原則通り、遺産分割協議等が必要となります。
遺言者が、長男Aの相続人にも遺産を承継して欲しいと考えていたなら、
「万一遺言者よりも先に長男Aが死亡した場合には、長男Aに相続させるとした財産は、長男の子Bに相続させる。」等の記載が必要でした。
遺言書の作成には、専門家のアドバイスを受けたほうが良いケースがありますね。
遺言書作成
遺言にまつわるエトセトラ
無理矢理遺言をさせたら・・・

<遺言にまつわるエトセトラ>
相続人が相続権を失うことがあります。
その一つが「相続欠格(そうぞくけっかく)」です。
事例は、親族が本人に「無理矢理」遺言させようとしたものです。
なお、本人には財産管理人(任意後見契約付)が就任していました。
<事例>
ある親族が認知症の進行が始まった本人に、自分に有利な遺言をさせようと企みました。
(本人の実印は財産管理人が管理していました。)
その親族は本人を連れ出し、市役所で実印の改印手続きをさせ、新しい印鑑で印鑑証明書を取得しました。
そして、その足で本人を公証人役場へ連れて行き、本人に任意後見契約を解除させて、かつ遺言公正証書を作成させようとしました。
公証人役場で本人が頑なに拒んだため、親族の企みは未遂に終わりました。
数日後、本人から(泣きそうな顔で)報告を受けて財産管理人が知り、対応しました。
もちろん、この親族の行為は許されるものではありません。
みなさまは、この話のどこに問題点を見つけましたか?
なお「相続欠格事由」は民法第891条に定められています。
遺言に関係した相続欠格事由が多いのでご案内します。
以下のような相続欠格事由にひとつでも該当することがあれば、法律上、「当然に」相続人の資格が剥奪されることになり、相続人ではなくなります。
民法第891条
第1号 省略
第2号 省略
第3号 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
第4号 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
第5号 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続欠格は、相続廃除のように、被相続人の意思による特段の手続を必要としません。
つまり、特定の相続人に上記の相続欠格事由が認められれば、その相続人は「当然に」相続権を失います。
相続が発生した際に、他の相続人が該当者に対して相続欠格事由を主張し、その主張が家庭裁判所で認められれば、該当者は「全く」相続できないのです。
遺言書保管制度について
遺言書作成
遺言執行者とは
相続法の改正について