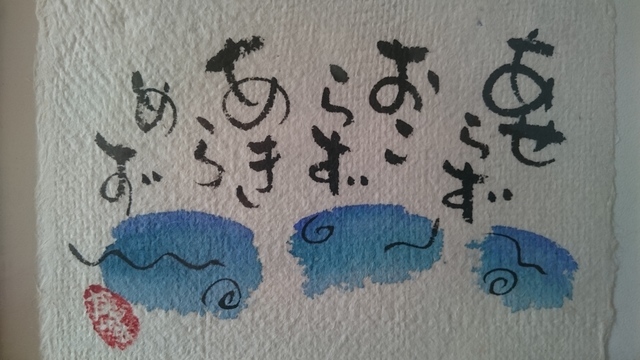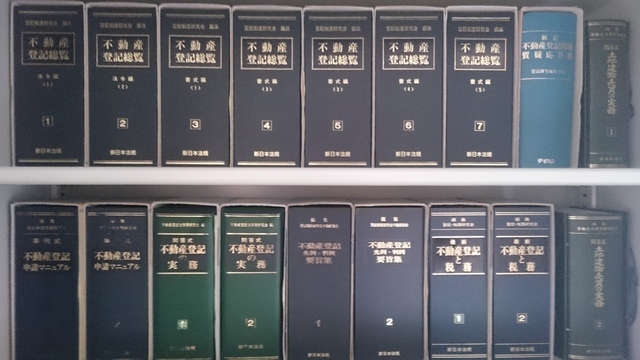0772-45-1686
遺産分割調停ってなに?(令和6年12月30日更新)
遺産分割調停って何でしょう?

遺産分割とは、
本人(被相続人)が遺言を残さずに死亡した場合、本人の遺産を相続人間でどのように取得するかを決定する手続のことです。
相続人間で、遺産分割協議が整わない場合には、各相続人は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
これは原則、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に申し立てる必要があります。
遺産分割調停で主張される内容は様々ですが、「前提問題」や「付随問題」といった、本来は遺産分割調停で審理する内容ではない理由で紛糾してしまうことがあります。
例えば、
「前提問題」とは、①相続人の範囲、②遺言書の存否及び有効性、③遺産分割協議の存否及び有効性、④遺産の範囲(遺産帰属性の問題)等があります。
この点で話が付かない場合は、調停を取り下げて、その前提問題を民事訴訟で解決してから、再度遺産分割調停を申し立てる必要があります。
「付随問題」とは、①葬儀費用の負担、②祭祀承継者の指定、③祭祀財産の承継に係る費用の負担、④使途不明金の問題(本人が亡くなる前に預金から引き出されたお金の行方等の問題)等があります。
これらの問題も、本来は遺産分割調停の審理対象ではないため、収拾が付かなくなる恐れがあります。
亡くなる前に「遺言」を残しておいてもらえれば(一番は、親族が仲良くしていれば)、防げたかもしれないお家騒動と言えます。
誰かを相続する限り、誰しも遺産分割を体験することになるのです。
相続手続
遺言書作成
遺産承継業務
身近な法律入門 遺産承継業務とは
身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ
本人訴訟支援、訴訟代理等
遺産分割調停の流れは?

遺産分割調停は裁判ではなく、「裁判所で行う話し合い」です。
つまり、当事者で合意するのですから、裁判所が勝手に裁いて決まる裁判よりも、当事者には「自分で決めた」という満足感のある結果を導くことが可能な手続きです。
前回は「前提問題」や「付随問題」といった、本論と離れた内容で紛糾するケースがあることをご紹介しました。
調停が成立しそうにない「ダメ」なケースでしたね。
ではここで、遺産分割調停はどのように進行するのか、実務での運用をご案内します。
家庭裁判所では、次の①から⑤の順番で、合意を重ねながら調停成立へ導いています。
①相続人の範囲の合意
↓
②遺産の範囲の合意
↓
③遺産の評価の合意
↓
④各相続人の取得額の合意
↓
⑤遺産の分割方法の合意
↓
調停成立
例えば、②遺産の範囲や③遺産の評価を飛び越して、いきなり④自分の取得額の主張を始める方がいらっしゃいますが、その主張に固執されると、調停が不成立に終わってしまうことが多いように思います。
その他、いきなりなされる主張として、
自分は被相続人の療養看護に努めたからもっとたくさんもらうべきだ(寄与分)という主張や、
あいつ(他の相続人)はたくさん生活費の援助をしてもらってるはずだから(特別受益)、相続分は減るはずだ、との主張がほとんどです。
でもそれは、④での「話し合い」で行う話です。
はやる気持ちは分かりますが、④まで待ってくださいね。
実際の話ですが、審判や裁判になっても「法定相続分」を基本に微調整した結果になることが多いと思われます。
つまり、調停でダメだったから審判や裁判で、法定相続分よりもたくさん貰おうと思っても、なかなか難しいということです。
そこまで知ってどう思われるでしょうか?
これから何年も親族と争いますか?
それとも、「今」調停で解決しますか?
それはおそらく、あなたの「考え方」次第で変わる結論です。
相続手続
遺言書作成
遺産承継業務
身近な法律入門 遺産承継業務とは
身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ
本人訴訟支援、訴訟代理等
調停に代わる審判とは

「調停に代わる審判」は、離婚調停における「面会交流」や「養育費」に関する事件、遺産分割調停等において、家庭裁判所が活用することがある手続です。
それは、次のような状態の時に有用であるとされています。
① 調停でほとんど合意できているのに、当事者の一方が裁判所に出頭することが困難な事案。
② 相手方が調停に一切出席せず、今後の出頭や対応も見込まれない事案。
③ 例えば養育費額について、わずかな差であるのに、当事者が心情的に合意できないといった事案等。
上記の状態の場合に、裁判所が調停手続きの中で「審判」として合意案を示します。
そして、双方から異議が出なければ、その内容で審判が確定し、合意が成立したこととする手続です。
異議が出たとしても、通常の審判手続きに自動的に移行する種類の手続きもあります。
家庭裁判所が「ちょっと背中を押す」感覚でしょうか。
「調停に代わる審判」を活用して、迅速・適正かつ柔軟な解決の実現が図られています。
身近な法律入門 子どものための面会交流
本人訴訟支援、訴訟代理等