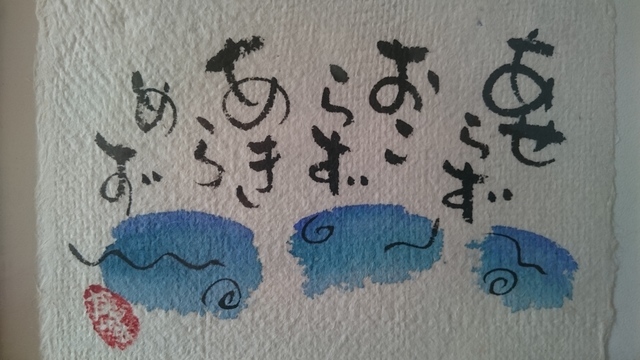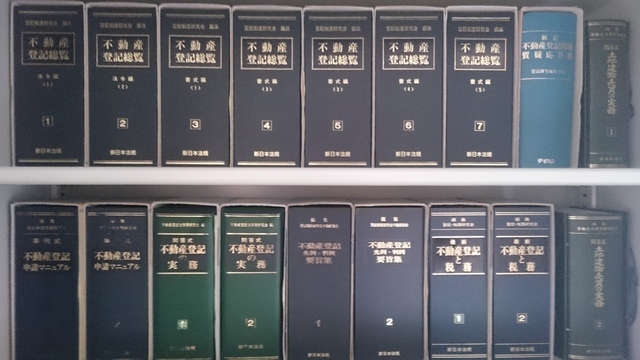0772-45-1686
成年後見人の家庭裁判所での手続きについて
(令和6年11月25日更新)
成年後見制度の開始申立について

成年後見制度に関しては様々な場面で、家庭裁判所への申立てが必要となります。
今回は「成年後見制度の開始」の場面でのお話をします。
*成年後見制度に関する詳細(例えば、どんな状況で利用する制度なのか等)は、ホームページの「成年後見制度とは http://www.kawakami-kyoto.com/579227828 」をご覧ください。
京都家庭裁判所では「後見申立セット」を配布しています。
この中には、申立書一式とその記載例があり、必要書類の一覧とその手配の仕方まで案内してあります。
ご自身や親族が申立てしようとする場合、施設や支援者が協力して申請する場合にはぜひ利用してください。
その申立書には「成年後見人等の候補者」を記載する欄がありますが、候補者がいない場合には、家庭裁判所が後見人名簿(司法書士・弁護士・社会福祉士)の中から、その事案に相応しい人を指定してくれます。
先ずは、申立ての段階で躊躇されませんように、ご案内申し上げました。
成年後見業務
成年後見業務とは
成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について
成年後見人の本人死亡後の死後事務について
成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)
成年後見人の家庭裁判所への業務報告について

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)に選任されると定期的に、家庭裁判所への業務報告が必要となります。
初回は審判確定後1か月程度の期限が定められて行う報告があります。
その際に、本人の財産目録や今後の収支予定表等を提出します。
その後は、原則1年ごとに業務報告をします。
本人の身上保護に関する報告や収支に関する報告(収支報告書や収支予定表、預貯金通帳のコピーや領収書のコピー等)が内容となります。
万一業務報告を怠ると、成年後見人等は家庭裁判所から解任されることになります。
そして、一度家庭裁判所から解任された成年後見人等は、もう二度と成年後見人等になることはできません(欠格事由)。
今回は「成年後見制度における業務報告」の場面でのお話をしました。
*成年後見制度に関する詳細(例えば、どんな状況で利用する制度なのか等)は、ホームページの「成年後見制度とは http://www.kawakami-kyoto.com/579227828 」をご覧ください。
https://www.courts.go.jp/.../katei/l4/Vcms4_00000397.html
京都家庭裁判所ホームページ(書式等が掲載されています)
成年後見業務
成年後見制度とは
成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について
成年後見人の本人死亡後における死後事務について
成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)
成年後見人が司法書士である場合の業務報告について

前回は、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)に選任されると定期的に、家庭裁判所への業務報告が必要であることをお伝えしました。
さらに重ねて、成年後見業務を行う司法書士は「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下「リーガルサポート」と言う。)」へも業務報告を行います。
こちらは原則、半年に1回の報告が必要で、家庭裁判所への報告よりも回数が多く、報告内容も詳細です。
(リーガルサポートの会員は司法書士のみですが、定額会費と会員が案件ごとに受けた個別の報酬から算出した定率会費を徴収して運営しています。)
業務報告を怠ると、会員はリーガルサポートの名簿から抹消されます(強制退会)。
成年後見人等の業務は、大きく身上保護業務と財産管理業務に分かれますが、その両方の業務を誠実に行っている事の証明を求められるのです。
今回も「成年後見制度における業務報告」の場面でのお話をしました。
*成年後見制度に関する詳細(例えば、どんな状況で利用する制度なのか等)は、ホームページの「成年後見制度とは http://www.kawakami-kyoto.com/579227828 」をご覧ください。
成年後見業務
成年後見制度とは
成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について
成年後見人の本人死亡後における死後事務について
成年後見制度の居住用不動産の処分許可申立について

成年後見制度に関しては様々な場面で、家庭裁判所への申立てが必要となります。
今回は「居住用不動産の処分」の場面でのお話をします。
*成年後見制度に関する詳細(例えば、どんな状況で利用する制度なのか等)は、ホームページの「成年後見制度とは http://www.kawakami-kyoto.com/579227828 」をご覧ください。
この処分には「売却」はもちろんのこと、本人が住んでいた借家契約の「解約」も含まれます。
本人の生活の本拠を失う可能性のある重大な行為であるので、家庭裁判所の許可を必要としているのです。
成年後見制度には本人保護のために様々な場面で家庭裁判所の監督があることをご案内しています。
安心して成年後見制度をご利用いただきたいと思います。
http://www.kawakami-kyoto.com/15962656301320
川上司法書士事務所ホームページ 身近な法律入門 成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について
成年後見業務
成年後見制度とは
成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について
成年後見人の本人死亡後における死後事務について
成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託について

成年後見人は本人の収支について把握する必要があります。
また、身寄りのない方の場合、お手紙をくださる方は重要な本人の支援者となり得ます。
しかし、本人が郵便物を管理できない場合(郵便物を開封しない、捨ててしまう等)には、必要な情報を見逃してしまいます。
その場合には、家庭裁判所に申し立てて、本人宛への郵便物を成年後見人宛に回送してもらえる制度があります。
この制度は回送嘱託の審判確定後6か月間有効で、延長するには特別な理由を疎明して再度申立てする必要があります。
これにより成年後見人の住所に請求書が届くことがあり、本人の債務の確認ができます。
その他、本人の知人からの年賀状などもあり、私はそれに返事をお送りしたりしています。
今回は「成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託」についてお話ししました。
*成年後見制度に関する詳細(例えば、どんな状況で利用する制度なのか等)は、ホームページの「成年後見制度とは http://www.kawakami-kyoto.com/579227828 」をご覧ください。
成年後見制度には本人保護のために様々な場面で家庭裁判所が関与します。
安心して成年後見制度をご利用いただきたいと思います。
成年後見業務
成年後見制度とは
成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について
成年後見人の本人死亡後における死後事務について
成年後見人の報酬付与の許可申請について

成年後見人の報酬は、家庭裁判所の許可を得て、本人の財産から支払われます。
事案でご紹介しましょう。(特定できないように多少の脚色をしています。)
本人は身体及び精神障害者で入院していた。
入院中に配偶者が死亡し、本人の世話をする者が一人もいなくなった。
本人には遠方に住む子供がいたが、病院・市役所・警察・裁判所からの問い合わせにも一切応じなかった。
配偶者の火葬は市が行った。
本人の自宅は借家であり、未払い賃料が月々滞納し続けている。
入院費やクリーニング代、家賃の未払い金が数十万円の負債となっている。
本人の預金残高はその負債額とほぼ同額であった。
市長申立で成年後見人に私が就任した。
成年後見人就任後、本人の子供と連絡をつけ、遺産分割協議を行った。
負債を返済した。
家庭裁判所の居住用不動産の処分許可を得て、借家の賃貸借契約を解除した。
借家にあった家財を搬出、処分した。
入院先の病院から「暴れる」との苦情を受けて退院を迫られ、遠方(片道1時間)の病院に転院した。
転院の付き添い、退院入院の手続きは成年後見人が行った。
本人とは月に一度の面談を継続し、本人の希望と生活状況の確認を行った。
ちなみに、前の病院では難聴とされ、筆談していたが、
転院先の病院で看護師が耳垢を取ってくれたところ、普通に聞こえるようになった。
新しい病院のスタッフとは、本人の残存能力の維持・回復について協議し、リハビリを始めた。
前の病院では、寝たきりで、排尿・排便後に巡回した看護師にオムツ交換されていたが、
転院後は、尿意や便意を感じた時点でナースコールし、自分でトイレで排尿・排便するようになった。
さらに、積極的にリハビリの提案を受け入れ、自ら歩行訓練を始めた。
そして、十数年ぶりに自分の足で歩行できるようになった。
本人が尊厳を取り戻したように見えた。
新しい病院で看護師に尋ねたところ、「前の病院からは危険人物として申送りがありましたが、そんなことは一切ありません」と教えてもらった。
むしろ本人は、看護師に対しても気遣いをしてくれるとのことで、病院スタッフからの評判も良い。
そして、私の顔を見ると、いつも「川上さーん」と言って、遠くからでも笑顔で手を振ってくれた。
そんな笑顔も、私の業務に対するモチベーションとなった。
ご参考までに、この案件で家庭裁判所から許可された、1年分の私の報酬が、金28万1,880円であったことをお知らせいたします。
成年後見業務
成年後見制度とは
成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について
成年後見人の本人死亡後における死後事務について
成年後見人の本人死亡後の死体の火葬に関する許可申立てについて

成年後見制度に関しては様々な場面で、家庭裁判所への申立てが必要となります。
今回は「本人死亡後の死体の火葬」の場面でのお話をします。
この火葬許可申立は、成年後見制度の中でも成年後見人のみに認められています(保佐人、補助人、任意後見人は認められていません)。
実務上の必要性から、平成28年に民法873条の2が新設されましたが、
本人の死後における事務に成年後見人等は苦悩しています。
本人死亡後の事務についてはこちらをご覧ください。
http://www.kawakami-kyoto.com/15984386822372
川上司法書士事務所ホームページ 身近な法律入門 成年後見人の本人死亡後における死後事務について
成年後見人の資格は本人の死亡時点で消滅します。
その後は、管理の計算と相続人への相続財産の引継業務のみが残ります。
しかし、本人死亡後の対応を相続人が誰も行わないことがあるのです。
平成28年の民法改正では、成年後見人による「火葬」の許可申請は認められましたが、「葬式」は今まで通り認められません。
成年後見人が家庭裁判所の許可を得て、本人の遺産から支出できる費用は、「火葬代」と「永代供養(低額な方法に限る)」「納骨代(低額な方法に限る)」とご理解ください。
「火葬」も「本人死亡後の預貯金からの出金」も、家庭裁判所の許可を必要としているのです。
成年後見制度には、本人保護のために様々な場面で家庭裁判所の監督があることをご案内しています。
安心して成年後見制度をご利用いただきたいと思います。
*成年後見制度に関する詳細(例えば、どんな状況で利用する制度なのか等)は、ホームページの「成年後見制度とは http://www.kawakami-kyoto.com/579227828 」をご覧ください。
成年後見業務
成年後見制度とは
成年後見人の財産管理業務と空き家空き地問題について
成年後見人の本人死亡後における死後事務について
成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について(死後事務)