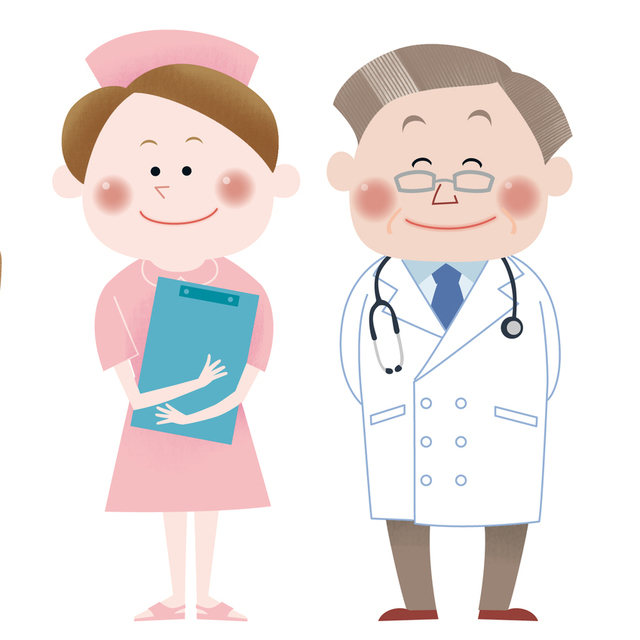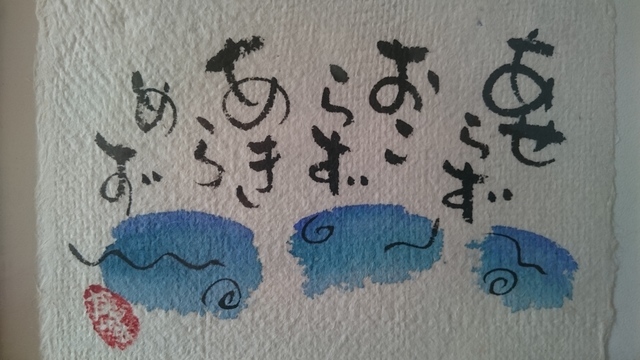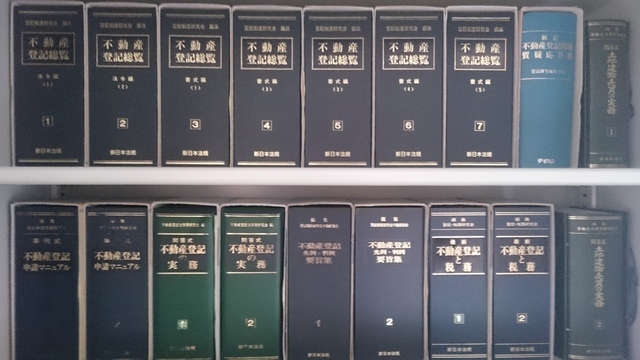0772-45-1686
未成年後見制度について(令和6年11月27日更新)
未成年後見制度とは

「未」成年後見制度のご紹介をしたいと思います。
読んで字のごとく、未成年者の支援をするための後見制度ですが、まだ皆様にとっては馴染みの少ない言葉かもしれません。
未成年後見人は、未成年者に対して親権を行使する者がいない場合等に選任されます(民法第838条1項)。
「親権を行使する者がいないとき」とは、親権者の死亡や失踪宣告、親権の喪失・停止・辞任等、法律上親権を行使できない場合と、親権者の行方不明、長期不在、心神喪失、精神病による長期入院、心身の著しい障害、受刑等により、事実上親権を行使できない場合があります。
未成年後見人の年間の申立件数は、東日本大震災時(平成23年)には3千人を超えたのですが、その後は2千件台で推移しており、成年後見制度の年間申立件数の約4万件と比べても、利用数の少なさが分かります。
ところで、令和3年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は20万8千件を超え、平成23年度の59,919件から、10年間で約3.5倍増加しています。
その中には、親が家庭裁判所から親権の喪失や停止、管理権の喪失の審判を受けたケースもあるでしょう。
また、事実上親権を行使できない状態の親もあるでしょう。
つまり、未成年後見制度の利用を必要とする未成年者の数は、実際はもっと多いと考えられるのです。
制度利用に繋がらない原因は、改めてご紹介したいと思います。
では、未成年後見制度利用の要件や、未成年後見人の権利義務と業務内容等について、成年後見制度との違いも確認しながら、数回に分けてご案内したいと思います。
一緒に学びましょう。
成年後見制度とは
成年後見業務
未成年後見人の選任方法と権利義務
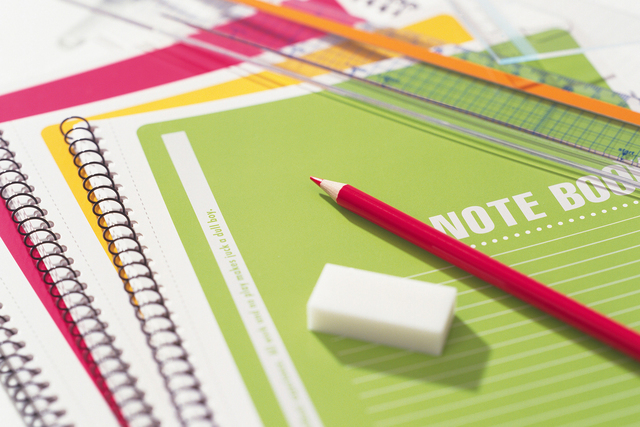
前回、未成年後見人は、未成年者に親権を行使する者がいない場合等に選任されることをお知らせしました。
では問題です。
Q.未成年者の両親が離婚し、母親が親権者となりましたが、その母親が死亡しました。その場合の親権者は誰になるのでしょうか?
答えを次の二つからお選びください。
①父親の親権が復活する。
②親権者がいなくなる。
<未成年後見人の選任方法>
未成年後見人の選任の方法は、法律上2つあります。
一つは、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定する方法(民法第839条1項)。
もう一つは、未成年者本人又はその親族、その他利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任する方法(民法第840条)。
家庭裁判所で選任された未成年後見人は、家庭裁判所に監督され、業務報告を行うことになります。
家庭裁判所とは、成年後見人とほぼ同様の関係になります。
しかし、遺言で指定された未成年後見人は、申告がなければ、家庭裁判所は把握できないことになります。
これは監督上、非常に不都合なことでありますが、現実に遺言で指定された未成年後見人はほとんど存在しないことから、問題は生じていないようです。
<未成年後見人の権利義務>
未成年後見人は、親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法第857条)。
つまり、親権者と同じ権限を有することになりますが、未成年後見人の身上監護義務には「善管注意義務」が課されており(民法第869条 第644条)、親権者の「自己のためにするのと同一の注意義務」(民法第827条)よりも、より高度な注意義務(重い責任)を課されています。
具体的に、未成年後見人が有する親権者と同一の権利義務について箇条書きしておきます(下記1~3を民法第857条が準用)。
1.監護教育義務(民法第820条)
2.居所指定権(民法第822条)
3.職業許可権(民法第823条1項)
4.財産管理権(民法第859条)
5.医療同意権(学説)
cf. 成年後見人には医療同意権はない
*令和4年12月10日、民法等の一部を改正する法律が成立し、懲戒権に関する規定は削除されました。
A.最初の問いの答えは「②親権者がいなくなる」でした。
成年後見制度とは
成年後見業務
成人年齢の引き下げ

「民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律」が、令和4年4月1日から施行されました。
それと同時に、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女の婚姻開始年齢が統一されました。
ところで、未成年後見の終了事由の1つに「未成年者が成年に達したとき」があります。
未成年後見が開始している事例の中には、両親を事故で亡くした場合等、多額の保険金が入り、未成年後見人が管理する財産が多いケースもあります。
未成年後見が終了した場合、未成年後見人は管理する未成年者の財産を、未成年者に引き継ぐことになりますが、18歳といえば、高校を卒業する前です。
中には自立には程遠い若者もいます。
みなさんのお子さんや、みなさん自身が18歳だった頃を思い出して下さい。
法律上成人したとはいえ、18歳になりたての若者が、未成年後見人から引き継いだ財産を自分で管理し、自分で資金計画して、進学や就職の道を一人で選択していかなけらばならなくなるのです。
未成年者は、高齢者と同じく、消費者被害等に遭う危険性が高いため、やはり心配ですよね。
そういった背景も知った上で、未成年後見人の権利義務について考えてみると、学びも深くなるように思うのですが、いかがでしょうか。
成年後見制度とは
成年後見業務
就任時における未成年後見制度と成年後見制度の違い
家庭裁判所で未成年後見人が選任された場合、未成年後見人に告知がなされますが、それは選任審判書を特別送達する方法がとられます。
告知がなされることは、成年後見人が選任された場合と同じなのですが、成年後見人の場合は、告知を受けてから(選任審判書の特別送達を受理してから)2週間の経過により審判が確定し、選任の効力が発生します。
成年後見人選任の場合のこの2週間は、即時抗告(異議申し立てのこと)をすることができる期間です(家事事件手続法第123条)。
しかし、未成年後見人の場合は、告知を受けたときに効力が生じ、確定します(家事事件手続法第74条2項)。
選任時にはもう一つ、成年後見制度と未成年後見制度の違いがあります。
それは、資格を証する書面です。
成年後見人の場合は、東京法務局において、成年後見人の登記がされますので、その登記事項証明書の発行を受けて、成年後見人であることの資格証明書として利用します。
しかし、未成年後見人の場合は、未成年者の戸籍に、未成年後見人の氏名と本籍等が記載されますので、その未成年者の戸籍謄抄本(全部事項証明書)が、未成年後見人の資格証明書となるのです。
つまり、未成年者の戸籍には、未成年後見人が専門職の第三者であったとしても、その本籍や戸籍上の氏名という、個人情報が記載されるため、このことも未成年後見制度の利用を見送る理由だと言われています。
さて、未成年後見人は、選任されて1か月程度の間に、家庭裁判所に財産目録や収支予定表などの提出をして初回報告を行いますが、これは成年後見制度と同じ流れで、報告書もほぼ同じ様式を利用しているようです。
後見人は、この財産目録の提出前は、急迫の必要がある行為しかする権限がありませんので、できるだけ早く出したいところです。
未成年後見で検討する収支予定は、成年後見とは少し視点が異なると思います。
本人の申告だけでなく、収支を裏付ける資料の収集が必要なことは同じですが、例えば「遺族年金」を受給している場合は異なります。
未成年者が両親の遺族年金を受給している場合、18歳になった年度の3月31日で支給が終了するので、いつまでも入金があるものとして将来設計すると、未成年者の18歳成人により未成年後見が終了してから、未成年者が困ってしまうこともあり得ます。
未成年後見人は善管注意義務を負いますが、それは親権者よりも高度な注意義務であることを忘れないようにしましょう。
アルバイトだと収入が一定でなかったりするでしょうから、未成年後見人はより想像力を働かせて、財産管理をする必要があるかもしれません。
成年後見制度とは
成年後見人の家庭裁判所での手続きについて
未成年後見人の財産管理

前回は、未成年後見人が選任されてから、家庭裁判所への初回報告までを、成年後見人の場合と比較して、違いを確認しながらお話しをしてみました。
今回は、未成年後見人による財産管理についてです。
後見人は預貯金口座の入出金を把握しないと財産管理ができませんが、例えば、未成年者が労働している場合、その賃金は未成年者自身が受け取りを請求するものであり、親権者も未成年後見人も、未成年者の代わりに受領してはなりません(労働基準法第59条)。
つまり、その賃金が振り込まれる口座を、未成年後見人が完全に管理してしまうことは、未成年者の賃金を、未成年後見人が代わりに受領していることになってしまいかねません。
その場合どういう方法が良いのかは、未成年者の個性や、未成年後見人との相性もありますから、ケースにより異なるのでしょうが、未成年後見人は労働基準法違反に問われないように、十分注意しなくてはならないでしょう。
また、未成年者が反抗期を迎える年頃だと、高齢者とは違う管理の難しさがあるようです。
例えば、未成年後見人が証書を管理していたのですが、未成年者が生命保険証書の紛失届をして、自分で手続して、保険金を受領してしまった事例があったようです。
後見人はさぞ驚いた事でしょう。
成年後見制度では、本人が死亡した時に後見が終了しますが、未成年後見制度では、本人が成年に達した時に後見が終了します。
その違いは、成年後見人は、被後見人の尊厳ある人生の仕上げを支援しているのに対して、未成年後見人は、未成年者の危なげだけど懸命な巣立ちを支援するということになるのかもしれません。
法律が求めていることは同じ財産管理であり、家庭裁判所への報告事項も同じですが、きっとその性質は大きく違うのだと思います。
次回は、身上監護(身上保護)について学びたいと思います。
身上監護においては、未成年後見人にはできて、成年後見人にはできないことがあります。
さて、それは何でしょう?
次回までの宿題といたしましょう。
成年後見制度とは
成年後見人の本人死亡後における死後事務について
未成年後見人の身上監護(身上保護)について
今回は、身上監護(身上保護)についてです。
身上監護においては、未成年後見人にはできて、成年後見人にはできないことがあります。
さて、それは何でしょう?
<ヒント>
答えは、未成年後見人は親権を行う者と同一の権利義務を有する(民法第857条)ことから導かれます。
正解は、「医療同意」です。
成年後見人等は、医師や看護師等から医療同意書へのサインを求められることがよくありますが、成年後見人等には医療同意権はありません。
病院関係者も、理解力のある方ばかりではありませんので、成年後見人等が精神労働を強いられる場面です。
未成年者後見のお話しに戻ります。
医療現場では、医療を行うためには、患者本人の同意を得ることは当然です。
しかし、未成年者は医療行為に対する理解や判断能力が成熟していませんし、赤ちゃんなどは自ら意思表示もできません。そこで、親権者等から未成年者本人に代わる医療同意(代諾)を得ることで、医療機関は医療行為に関する違法性を阻却しようとするわけです。
なお、未成年者が治療を必要としているにもかかわらず、親権者等が医療同意をしないことで、必要かつ適切な医療を受けさせない行為のことを、「医療ネグレクト」といいますが、これは児童虐待の一類型です。
では、医療同意権は、成年後見人にはないのに、なぜ未成年後見人にはあると考えられているのでしょうか。
通常、親が自分の子供に対して身上監護を行う際に、それによって第三者に対して責任を負うことはありませんよね。
それと同じで、同意をした医療行為によって未成年者に重篤な事態が生じたとしても、通常の注意義務を怠ったなどの特段の事情がない限りは、その事の責任を親が問われることはないと解されます。
未成年後見人は親権者と同じ権利義務を有するので、この場合の理由が、未成年後見人にも当てはまるわけです。
しかし、未成年後見人の立場としては、未成年者本人や親族と十分に話し合い、場合によってはセカンドオピニオンを求める等、医療同意の判断をする前には、慎重な対応が求められることは間違いありません。
次回も引き続き、身上監護について学びましょう。
成年後見制度とは
親権の行使について
「親権」とは、子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であります。
つまり、「親権」は子どもの利益のために行使することと定められています。
そこで、未成年者に親権を行使する者がいない場合、又は親権者が親権を行使できない状態にある場合は、未成年後見人が選任されることになっています。
しかし、実際には上記の場合でも、児童福祉施設の施設長は、入所中の児童に親権を行使することになっています(児童福祉法第47条1項)。
しかも、親権者や未成年後見人が存在する場合においても、児童福祉施設長は、児童福祉のために監護・教育・懲戒について必要な措置ができ(児童福祉法第47条3項)、この場合、親権者も未成年後見人も、児童福祉施設長がとる措置を不当に妨げてはならないとされています(児童福祉法第47条4項)。
なお、児童相談所長も、親権者等が存在するに至るまでは、親権を行うことができます(児童福祉法第33条の2第1項、第47条2項)。
このように、児童福祉施設長の判断で身上監護がなされ、中でも児童養護施設の長は、学校教育法上の保護者に準ずるものとして、入所児童を就学させる義務を負っているため(児童福祉法第48条)、それにより保護者として小学校に就学させることになると、実際上、未成年後見人を選任する必要性に乏しくなるようです。
その他、未成年後見人が選任されていない未成年者と同居する親族は、児童福祉法上の「保護者」となりますが(児童福祉法第6条)、学校教育法上の「保護者」は親権を行使する者に限られますので(児童福祉法第16条)、学校教育法上の保護者には該当しないことになります。
なんだかややこしい仕組みですよね。
そして、「親族里親」(児童福祉法第6条の4第3号)は、児童相談所が児童を保護した上で、3親等内の親族に児童の委託をする制度です。この里親は児童養護施設長と同様の監護権を持ちます。
子供を取り巻く環境だけでなく、子供を保護するための法制度も少し複雑に感じますよね。
次回は養子縁組について学びたいと思いますが、これは法律上の親子になる法制度です。
子供にとっての最善の方法を検討するためには、親権を行使するための選択肢は、たくさん知っておく方が良いでしょう。
成年後見制度とは
未成年後見人と養子縁組について

今回は「養子縁組制度」についてです。
日本では、家という単位を重視する歴史があり、「後継ぎ」として家を継ぐ承継者を得るために養子縁組制度が利用されてきました。
養子縁組とは、血縁者でない者とも、法律上の親子関係になることができる制度です。
戦後は、「お家」承継のためにする目的以外にも、親権者のいない、又は保護を要する児童に対して、親に代わる養育の担い手を得るための制度として、利用が期待されています。
ところで、法律上は2種類の養子縁組があります。
一つは「普通養子縁組」(民法第792条以下)、もう一つは「特別養子縁組」(民法第817条の2以下)です。
特別養子縁組は、昭和62年の民法改正で新設された制度です。
その二つの養子縁組制度の大きな違いは、普通養子縁組の場合、縁組した子は実親との親子関係は継続したまま(実親の相続人となる)であるのに対して、特別養子縁組の場合は、縁組した子とその子の実親とは親子関係がなくなる(実親の相続人ではなくなる)ということです。
特別養子縁組は、より実の親子に近い関係を作り出すことを目的としており、戸籍上も「養子」ではなく、「長男」「長女」と記載されます。
そして、実の親子のようになるためには、養子縁組時において、子が幼少である必要があると考えられていたため、施行当初は、子の年齢は「6歳未満」とされていました(現在は子の年齢条件は15歳未満に引き上げられています)。
ちなみに、実際に里親となった者は、未成年後見人となるよりも、普通養子縁組で養親となるケースが多いようです。
ところで、未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です(民法第798条)。
おや?と思った方もいらっしゃると思います。
そうです。
自己の配偶者の直系卑属(連れ子)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要であり、市町村への届け出だけで養子縁組が可能なのです。
なお、未成年後見人が、その後見する未成年者と養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可が必要です(民法第794条)。
その許可の判断基準は、未成年者の福祉に合致するか否かですが、未成年者の現在及び将来の生活の妨げとなる縁組でなければ許可されるようです。
ただそれは、未成年後見人が、今後は「親」として、その未成年者と人生を歩もうと決心した場合のお話です。
次回は、子の責任は親が負うというお話をしたいと思います。
成年後見制度とは
成年後見人の家庭裁判所での手続きについて
未成年者の不法行為について~子の責任は親が負う~

今回は、子の責任は親が負うというお話しです。
未成年者が故意または過失により第三者に対して損害を与えた場合、未成年者自身が不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります(民法第709条)。
しかし、未成年者に責任弁識能力がない場合には、未成年者は損害賠償責任を負わない(民法第712条)代わりに、未成年者の監督義務者がその第三者に対して損害賠償責任を負うことになるのです(民法第714条1項)。
未成年者に責任弁識能力がない場合とは、自己の行為が違法なものとして法律上非難されることを弁識する精神能力がないという意味であり、道徳上悪い行為であると認識するレベルの能力のことではありません。
その能力の有無については、個別具体的な判断によることになりますが、一般的には、12歳前後の年齢であれば、責任弁識能力があるとされることが多いようです。
そして、その監督責任を負う監督義務者としては、その未成年者の監督について「法定の義務を負う者」であるとされていますから、親権者、そして未成年後見人も該当します。
成年後見人は「法定の義務を負う者」には該当しないとされていますから、この場合も、未成年後見人は成年後見人よりも高度な監督責任があるとされているのですね。
なお、監督義務者が監督責任を負う場合の要件は下記のとおりであり、民法第714条1項に記載があります。
1.加害者である未成年者が責任無能力者であること
2.責任無能力者の不法行為であること
3.監督義務を怠らなかったことの証明がないこと
4.監督義務者による因果関係の不存在の証明がないこと
この3と4の立証責任は監督義務者にあり、その立証が非常に困難であることから、裁判上で監督義務者が免責を受けることは稀といわれています。
これも、未成年後見人は未成年者の身上監護について、親権者と同一の権利義務を有する(民法第857条)からにほかなりません。
子の責任は親が負うというお話しでした。
成年後見制度とは
未成年後見制度の終了事由について

成年後見制度の終了事由に「本人の死亡」があるのと対に、未成年後見制度の終了事由には「未成年者が成年に達したとき」があります。
その違いは、成年後見人は、被後見人の尊厳ある人生の仕上げを支援しているのに対して、未成年後見人は、未成年者の危なげだけど懸命な巣立ちを支援するということになるのかもしれないと以前述べました。
その他の終了事由には、未成年者が養子縁組した場合、未成年後見人が辞任し、又は解任された場合があります。
なお、かつては成年擬制により終了することもありました。
成人年齢が20歳だった頃は、婚姻可能年齢が男18歳、女16歳だったため、未成年者が成人する前に婚姻することがありましたが、その場合、婚姻することにより20歳未満であっても成人に達したとみなす民法の規定があったのです。
未成年後見が終了すると、未成年後見人は2か月以内に管理の計算をして家庭裁判所に報告しますが、それは成年後見人と同じです。
後見終了時に異なる手続としては、未成年後見終了の日から10日以内にする、未成年者の本籍地又は未成年後見人の住所地の市町村役場への「後見終了届」があります。
未成年者の戸籍に、未成年後見人の本籍や氏名が記載されているので、終了届が必要となるのです。
その他、未成年後見制度の考え方と手続きの流れは、成年後見制度と類似しています。
しかし、収支予定の検討一つにしても、未成年後見人は、より想像力を掻き立てる必要があることも以前に述べました。
未成年者を巣立ちまで支援するということに、法律上負う善管注意義務以上に、未成年後見人はその職責を重く感じるのだろうと思います。
以上、未成年後見制度のお話をして参りました。
最後になりますが、先日、ある専門誌で、未成年者の里親になった方の投稿を読みました。
幼い子どもに大切なのは「愛着(アタッチメント)」であるとありました。
子どもが苦痛や恐怖を感じたとき、泣くことや大人に近づいてそれを伝えること、それをアタッチメントというそうです。
そうした場合に、特定の大人が共感的、かつ継続的に関わることで、子どもはその大人を絶対的に自分を守ってくれる存在(=安全基地)だと認識するそうです。
その安全基地ができることで、子どもは外の世界を探索することができ、不安を感じたらまた安全基地に戻ってくる。それをくり返して子どもは自立していくとありました。
子ども時代にそのアタッチメントの経験が不足すると、大人になってもなかなか他人を信じることができない、常に周囲に脅かされているように感じる、自己肯定感も低くなりがちで、諸々の発達障害と同様の特徴や精神疾患にもつながりやすくなると言われているそうです。
そして、児童相談所が、虐待家庭等から保護した児童を、里親家庭や施設で公的な責任の下に養育することを「社会的養護」といいますが、その対象児童は約4万2千人います(令和3年厚生労働省資料)。
未成年後見制度を学びながら、この里親家族のように、安全基地になれる大人が増えなければならないのだと思いました。
成年後見制度とは
成年後見人の本人死亡後における死後事務について
成年後見人の家庭裁判所での手続きについて
成年後見人の本人死亡直後から弔いまでの対応について